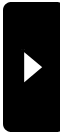› 介護の「ふくしあ」-スタッフブログ › ケアプランふくしあ-居宅介護支援
2020年06月10日
入梅
はじめまして。4月からケアプランふくしあで働いております市川と申します。以後よろしくお願い致します。
コロナに加えて気温の変動が大きくなりましたが、体調変わる事なく過ごせておりますでしょうか?
さて、本日は入梅です。梅雨入りです。週間天気を見てみると関東も週末から雨予報が増えています。いい機会だったので少し梅雨について調べてみました。
そもそも入梅は江戸時代に梅雨入りの時期を知る事は農家が田植えの日を決める上に重要とのことで目安として決めた日だそうです。なので実際の梅雨入りとずれたりするんですね。今よりも昔の方が天候に色々な事が左右されていたこともあり、各国で紀元前の頃から天気を予想していたそうですが、数値による天気予報は1955年(日本は1959年)から始まったそうです。意外と最近なんですね。加えてその頃は気象庁以外は天気予報を発信してはいけなかったそうで、全てのメディアの天気予報は気象庁発表だったそうです。なので、どこをみても天気予報は同じだったそうです。そして平成5年に天気予報が自由化され、気象庁以外の天気予報が流れるようになったそうです。本当に最近ですね。全く記憶になくて今回改めて調べてみて驚きましたが…皆様ご存知でしたでしょうか…
最初は梅雨について調べてみたのですが、そこから天気予報の歴史が入ってきました。インターネットってすごいですね。今では当たり前ですが、2000年代のインターネット、携帯電話の普及で朝の少しの時間でも天気予報を見れるようになったわけですから。
これ以上調べると、どんどん長くなってしまいそうなのでこの辺にしておきます。最後まで読んでいただいてありがとうございました。
雨男の市川が担当しました。
コロナに加えて気温の変動が大きくなりましたが、体調変わる事なく過ごせておりますでしょうか?
さて、本日は入梅です。梅雨入りです。週間天気を見てみると関東も週末から雨予報が増えています。いい機会だったので少し梅雨について調べてみました。
そもそも入梅は江戸時代に梅雨入りの時期を知る事は農家が田植えの日を決める上に重要とのことで目安として決めた日だそうです。なので実際の梅雨入りとずれたりするんですね。今よりも昔の方が天候に色々な事が左右されていたこともあり、各国で紀元前の頃から天気を予想していたそうですが、数値による天気予報は1955年(日本は1959年)から始まったそうです。意外と最近なんですね。加えてその頃は気象庁以外は天気予報を発信してはいけなかったそうで、全てのメディアの天気予報は気象庁発表だったそうです。なので、どこをみても天気予報は同じだったそうです。そして平成5年に天気予報が自由化され、気象庁以外の天気予報が流れるようになったそうです。本当に最近ですね。全く記憶になくて今回改めて調べてみて驚きましたが…皆様ご存知でしたでしょうか…
最初は梅雨について調べてみたのですが、そこから天気予報の歴史が入ってきました。インターネットってすごいですね。今では当たり前ですが、2000年代のインターネット、携帯電話の普及で朝の少しの時間でも天気予報を見れるようになったわけですから。
これ以上調べると、どんどん長くなってしまいそうなのでこの辺にしておきます。最後まで読んでいただいてありがとうございました。
雨男の市川が担当しました。
2020年06月03日
COVID-19(新型コロナウイルス)と経済
密林の中でチンパンジーが札束を数えてニンマリとしている、イルカがコインを加えて海の中でショッピングしているという事はない。生物界の中で貨幣というシステムを操るのは人間だけということは、それはホモサピエンスという種が持つ固有の癖ということである。文化人類学者のレヴィ=ストロースは、「人間社会は交換から始まる」と言っている。養老孟司氏は交換が可能になる為には等価交換(=)、ある物とある物が「同じ」という意識作用が前提条件だと指摘している。しかし、自然界では本来A=Bという関係が成り立つ物など何もないというのが厳然たる事実である。リンゴ1個=100円 ボールペン1本=100円 ∴リンゴ=ボールペンというもともと比較対象する事すらできない物を「同じ」として流通させる事は本質的には幻想でしかない。
貨幣が金本位制まではこの幻想性に一定の箍が嵌められていたが、変動為替相場制になり箍が外れ幻想性が病的に肥大したのが今の社会ではないのか。金融経済に於いてある会社の時価総額何兆円など、キャッシュレス社会の中で、電子デーダ上で利権のやり取りをしているだけではないのか。箍が外れた人間の癖によって構築された社会の足元をCOVID-19に掬われたというのが今の社会経済状況のような気がする。
正直、60年以上生きて来て私は未だに貨幣というものがよく分からない。貨幣の事がよく分からず、かつ、いざとなれば尻を拭く事も出来ない紙切れになる可能性のある日本銀行が発券する諭吉の熱心な信者にもなれない私が貧乏であるという事はよく分かる。
3年毎に行われる介護報酬改定の際に、必ず抑制圧力を主張してくる経団連は社会保障に対して、正真正銘お荷物だと思っているのだろう。COVID-19の問題で大企業が経営破綻の危機に陥った場合には、以前、金融機関に行ったように公的資金を資本に投入することも囁かれているようだが、要するに企業丸ごとの生活保護対策みたいなものだろう。ちょっとした条件の変化で人は救済(お荷物と思われる)される側に立たされるという事である。中井久夫氏が『看護のための精神医学』の中で「だれも病人でありうる、たまたま何かの恵みによっていまは病気でないのだ」という謙虚さが、病人とともに生きる社会の人間の常識であると思う、と著している。病人を困窮(病人=困窮)に置き換えてもそのまま人としての振舞いの指針として成立すると思うが、上層の人々にはどうでもいい事なのかも知れない。このコロナ禍の中にあっても内閣は経済財政諮問会議を利用し全国の公立・公的病院の内424の病院を統廃合させ、最大で20万床のベッドを減らすよう厚生労働省に指示を出しているが、それを考え直す気は全く無い様である。
エコノミクス(経済学)の語源であるギリシャ語の『オイコノミクス』とは、「共同体の在り方」を意味する言葉だそうです。漢語における「経済」とは、「世の中を治め、人民を救う」ことを意味する経世済民(若しくは経国済民)の略語だそうです。
貧乏の「乏」は白川静によれば「仰向けの死体の形」という事である。社会的動物である人間にとって究極の貧乏は死を意味するのであろう。
このコロナ禍が、人間の癖をいたずらに肥大化させる市場原理主義的な社会に大きなダメージを与え、期せずして互助互恵による人間の連帯性を尊重する経済社会へと、価値の機軸が変り、自然的・社会的・個人的人間として調和の取れた生き方ができる世界への転換点となるのであれば、それは、今の大人達にとっては受難かもしれないが、次世代にとっては福音になる可能性を秘めているのかも知れない。
「人間は自分自身の歴史をつくる。だが、思うままではない。自分で選んだ環境のもとではなくて、すぐ目の前にある、与えられた、持ち越されてきた環境のもとでつくるのである。」(カール・マルクス:「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日」)
人間の癖を肥大化させてきた結果もたらされている気候変動や原発問題など、私たちは次世代に対して何を持ち越させようとしているのだろうか。そもそも自然は人間の癖を成立させるために存在している訳ではない。レヴィ=ストロースが言うように、世界は人間なしに始り、人間なしに終わっても何の不思議もない。今、人間の意図とは全く関係なしに有効な環境対策が世界中で行われている。
パパラギ(白人)は一種特別な、そして最高にこんがらがった考え方をする。彼はいつでも、どうしたらあるものが自分に役立つか、そしてどうしたら自分の権利になるかと考える。それもたいてい、ただ一人だけのためであり、皆のためではない。
パパラギはこうも言う。「このヤシはおれのものだ」なぜかというと、ヤシはそのパパラギの小屋の前に生えているから。まるでヤシの木を、自分で生やしでもしたかのように。ヤシは、決してだれのものでもない。ヤシは、大地から私たちに向かって差し伸べもうた神の手だ。神はたくさんの手を持っておられる。どの木も、どの花も、その草も、海も空も、空の雲も、すべてこれらは神の手である。私たちは手を握って喜ぶことは許されている。だがしかし、こう言ってはならない。「神の手は俺の手だ」しかしパパラギはそう言うのだ。
(パパラギより)
ケアプランふくしあ 木藤
貨幣が金本位制まではこの幻想性に一定の箍が嵌められていたが、変動為替相場制になり箍が外れ幻想性が病的に肥大したのが今の社会ではないのか。金融経済に於いてある会社の時価総額何兆円など、キャッシュレス社会の中で、電子デーダ上で利権のやり取りをしているだけではないのか。箍が外れた人間の癖によって構築された社会の足元をCOVID-19に掬われたというのが今の社会経済状況のような気がする。
正直、60年以上生きて来て私は未だに貨幣というものがよく分からない。貨幣の事がよく分からず、かつ、いざとなれば尻を拭く事も出来ない紙切れになる可能性のある日本銀行が発券する諭吉の熱心な信者にもなれない私が貧乏であるという事はよく分かる。
3年毎に行われる介護報酬改定の際に、必ず抑制圧力を主張してくる経団連は社会保障に対して、正真正銘お荷物だと思っているのだろう。COVID-19の問題で大企業が経営破綻の危機に陥った場合には、以前、金融機関に行ったように公的資金を資本に投入することも囁かれているようだが、要するに企業丸ごとの生活保護対策みたいなものだろう。ちょっとした条件の変化で人は救済(お荷物と思われる)される側に立たされるという事である。中井久夫氏が『看護のための精神医学』の中で「だれも病人でありうる、たまたま何かの恵みによっていまは病気でないのだ」という謙虚さが、病人とともに生きる社会の人間の常識であると思う、と著している。病人を困窮(病人=困窮)に置き換えてもそのまま人としての振舞いの指針として成立すると思うが、上層の人々にはどうでもいい事なのかも知れない。このコロナ禍の中にあっても内閣は経済財政諮問会議を利用し全国の公立・公的病院の内424の病院を統廃合させ、最大で20万床のベッドを減らすよう厚生労働省に指示を出しているが、それを考え直す気は全く無い様である。
エコノミクス(経済学)の語源であるギリシャ語の『オイコノミクス』とは、「共同体の在り方」を意味する言葉だそうです。漢語における「経済」とは、「世の中を治め、人民を救う」ことを意味する経世済民(若しくは経国済民)の略語だそうです。
貧乏の「乏」は白川静によれば「仰向けの死体の形」という事である。社会的動物である人間にとって究極の貧乏は死を意味するのであろう。
このコロナ禍が、人間の癖をいたずらに肥大化させる市場原理主義的な社会に大きなダメージを与え、期せずして互助互恵による人間の連帯性を尊重する経済社会へと、価値の機軸が変り、自然的・社会的・個人的人間として調和の取れた生き方ができる世界への転換点となるのであれば、それは、今の大人達にとっては受難かもしれないが、次世代にとっては福音になる可能性を秘めているのかも知れない。
「人間は自分自身の歴史をつくる。だが、思うままではない。自分で選んだ環境のもとではなくて、すぐ目の前にある、与えられた、持ち越されてきた環境のもとでつくるのである。」(カール・マルクス:「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日」)
人間の癖を肥大化させてきた結果もたらされている気候変動や原発問題など、私たちは次世代に対して何を持ち越させようとしているのだろうか。そもそも自然は人間の癖を成立させるために存在している訳ではない。レヴィ=ストロースが言うように、世界は人間なしに始り、人間なしに終わっても何の不思議もない。今、人間の意図とは全く関係なしに有効な環境対策が世界中で行われている。
パパラギ(白人)は一種特別な、そして最高にこんがらがった考え方をする。彼はいつでも、どうしたらあるものが自分に役立つか、そしてどうしたら自分の権利になるかと考える。それもたいてい、ただ一人だけのためであり、皆のためではない。
パパラギはこうも言う。「このヤシはおれのものだ」なぜかというと、ヤシはそのパパラギの小屋の前に生えているから。まるでヤシの木を、自分で生やしでもしたかのように。ヤシは、決してだれのものでもない。ヤシは、大地から私たちに向かって差し伸べもうた神の手だ。神はたくさんの手を持っておられる。どの木も、どの花も、その草も、海も空も、空の雲も、すべてこれらは神の手である。私たちは手を握って喜ぶことは許されている。だがしかし、こう言ってはならない。「神の手は俺の手だ」しかしパパラギはそう言うのだ。
(パパラギより)
ケアプランふくしあ 木藤
2020年02月28日
もうすぐ春なのに・・・
今 家に帰りテレビをつけると、新型コロナウイルスの話題ばかりです。
予防の方法は知られているのに、一つの手段であるマスク、消毒液が売り切れでは。
今はやれることから、続けましょう。 手洗い。うがい。そして、顔を頻繁に触らないことも大切です
そして一刻も早く事態が収束し、安心してお花見でもできるようになりたいですね
さて、今回は誤嚥性肺炎について少し書いてみます。
「誤嚥性肺炎」とは・・・???
唾液や口の中で増えてしまった細菌が気付かないうちに、誤って気道に入り込むことで起きる「肺炎」のことを言い
口の機能が低下した高齢者や、寝たきりの状態の方に起こりやすいです。
予防法として
口の中の細菌数を減らすことが重要で、乾燥予防と歯磨きで口の中の清潔を保つことが大切です。
食後すぐに歯磨きができない時は「うがい」が効果的。
その他、デイサービスでも行われている 嚥下体操(えんげたいそう)も予防になります
嚥下とは飲み込みの事。口から食べ物が入って食道へ送り込む一連の動きの事。
年と共に舌や口の周り、首などの筋肉も固くなり鍛えることが必要になります。
舌の体操
口の両端や鼻の下などいろいろな方向に動かします
頬の体操
ほほを膨らませたりすぼめたりします
首の体操
左右に傾けたり、左右にゆっくり1回ずつ回します
食事の前に毎日続けられたらいいですね。
ケアプランふくしあ 檜木ゆかり
予防の方法は知られているのに、一つの手段であるマスク、消毒液が売り切れでは。
今はやれることから、続けましょう。 手洗い。うがい。そして、顔を頻繁に触らないことも大切です

そして一刻も早く事態が収束し、安心してお花見でもできるようになりたいですね

さて、今回は誤嚥性肺炎について少し書いてみます。
「誤嚥性肺炎」とは・・・???
唾液や口の中で増えてしまった細菌が気付かないうちに、誤って気道に入り込むことで起きる「肺炎」のことを言い
口の機能が低下した高齢者や、寝たきりの状態の方に起こりやすいです。
予防法として
口の中の細菌数を減らすことが重要で、乾燥予防と歯磨きで口の中の清潔を保つことが大切です。
食後すぐに歯磨きができない時は「うがい」が効果的。
その他、デイサービスでも行われている 嚥下体操(えんげたいそう)も予防になります
嚥下とは飲み込みの事。口から食べ物が入って食道へ送り込む一連の動きの事。
年と共に舌や口の周り、首などの筋肉も固くなり鍛えることが必要になります。
舌の体操

口の両端や鼻の下などいろいろな方向に動かします
頬の体操
ほほを膨らませたりすぼめたりします
首の体操
左右に傾けたり、左右にゆっくり1回ずつ回します
食事の前に毎日続けられたらいいですね。

ケアプランふくしあ 檜木ゆかり
2020年02月21日
見上げてごらん夜の星を
梅や水仙など早春の花が見ごろですね。日も冬至の頃より伸びてきましたが、仕事を終え、帰宅し犬の散歩をする頃は日が落ち、空には星が輝き始めています。
春日部辺りでも空気が澄んでいる冬の夜空はそれなりに星が輝いており、散歩をしながらそれを眺めるのが楽しみとなっています。
すぐに目につくのは冬の代表的な星座のオリオン座ですが,それがこの冬は輝きが弱いような気がして、気のせい?それとも目の老化のせい?と考えておりました。
そうしたらなんとオリオン座の右肩の位置にある赤星超巨星ベテルギウスがこれまでの半分くらいの明るさになっているという新聞記事を見つけました。超新星爆発を起こすのではないかと話題になっているそうです。
地球から700光年の距離にあり800万歳で半径が太陽の1000倍もある巨大な星の寿命が終わろうとしているそうですが宇宙の事なので爆発は明日かもしれないが10万年後かもしれない。もしかしたら実はすでに爆発していて、光が届いて私たちが確認できるのは700年後かもしれないと書いてありました。
天文学の事はよくわかりませんが壮大なスケールの事を考えながら空を見上げていると1日の疲れが吹き飛ぶ気がします。
星空を見るという事は、遠くを見るという事で、遠くを見ると、目の筋肉がリラックスし頭痛や肩こりにも良いようです。
また、背筋がスーッと伸び自然と呼吸もゆっくり深呼吸になり気持ちも落ち着きます。
以上 星空観賞のおかげで寒い日の夜の犬の散歩がくじけずに行けている黒田でした。
春日部辺りでも空気が澄んでいる冬の夜空はそれなりに星が輝いており、散歩をしながらそれを眺めるのが楽しみとなっています。
すぐに目につくのは冬の代表的な星座のオリオン座ですが,それがこの冬は輝きが弱いような気がして、気のせい?それとも目の老化のせい?と考えておりました。
そうしたらなんとオリオン座の右肩の位置にある赤星超巨星ベテルギウスがこれまでの半分くらいの明るさになっているという新聞記事を見つけました。超新星爆発を起こすのではないかと話題になっているそうです。
地球から700光年の距離にあり800万歳で半径が太陽の1000倍もある巨大な星の寿命が終わろうとしているそうですが宇宙の事なので爆発は明日かもしれないが10万年後かもしれない。もしかしたら実はすでに爆発していて、光が届いて私たちが確認できるのは700年後かもしれないと書いてありました。
天文学の事はよくわかりませんが壮大なスケールの事を考えながら空を見上げていると1日の疲れが吹き飛ぶ気がします。
星空を見るという事は、遠くを見るという事で、遠くを見ると、目の筋肉がリラックスし頭痛や肩こりにも良いようです。
また、背筋がスーッと伸び自然と呼吸もゆっくり深呼吸になり気持ちも落ち着きます。
以上 星空観賞のおかげで寒い日の夜の犬の散歩がくじけずに行けている黒田でした。
2020年02月04日
環境問題
グレタ・トゥンベリさんの環境活動や近年の気候変動などを環境問題がクローズアップされている。
水洗トイレや蛇口を捻ればお湯が出るという事が当たり前ではないと言われて、そう言われればそうかも知れないと体験的に振り返る事が出来るのは昭和30年代生まれまでだと思う。
このブログをアップするのにも閲覧するにもエネルギーコストが掛かっている。企業から殆ど閲覧されることなく、ただ削除されるだけの莫大なメールがユーザーに送信されている。送信にも削除にもエネルギーコストが掛かっている。(ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、モネロの主要な4種類の仮想通貨のマイニングだけでキューバの使用電力と同じ程度になっていると推計されており、電力消費の限界で仮想通貨は破綻するという予想もあります。:月尾嘉男氏)
日本では、年間2,759万トンの食品廃棄物等が出されている。このうち、まだ食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は643万トン。これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食糧援助量(平成29年で年間約380万トン)の1.7倍に相当します。また、食品ロスを国民一人当たりに換算すると"お茶腕約1杯分(約139g)の食べもの"が毎日捨てられているそうです(農林水産省及び環境省「平成28年度推計」)。食料自給率はカロリーベースでは37%で後の63%は輸入という事である。実質的には何も生みだす事のない食料生産、物流、廃棄にエネルギーだけを消費し経済成長したと喜んでいるのである。昔の常識人であれば、罰当たりと言ったであろう。
物質循環という視点から今の経済活動が抱えている本質的問題を指摘したのは、養老孟司氏(バカの壁)だと思う。樽に入っている酒を八ちゃんと熊ちゃんが互いに酌み交わしながら酒を売買している構図(花見酒)が今の経済活動だと。酒を石油に置き換えたのが現代社会である。この問題を経済の専門家であるアナリスト達が全く指摘しないのは何故なのだろうか?
私たちは炭素循環だけでなく大気中の窒素ガスと水素ガスを反応させてアンモニアを合成させる「ハーバー・ボッシュ法」の開発により窒素循環も大きく変えている。大河内直彦氏によれば、「人類は大量のエネルギーをアンモニア合成につぎ込んでいる。その量は1年間になんと5000兆キロジュールにも達する。これは大型の原発150基分にも相当する莫大な量」という事だそうです。このアンモニアをもとに硫安などの窒素肥料が作られ食料生産が飛躍的に伸び、人口爆発につながっている。化学肥料などがなかった頃の農家が窒素を土に還元するためにどれくらい苦労していたか。昔、水田でレンゲを栽培していたのもマメ科植物と共生する根粒菌による窒素固定を利用したものである。先人の知恵である。
月尾嘉男氏よれば、「人類の歴史を500万年とすると、その99%の期間は狩猟採集生活で、1人の人間が1日に消費するエネルギーは2500キロカロリー程度でした。1万年前くらいに農業を手中にすると、耕作に牛馬を使ったり、灌漑に風車を使ったりするようになり、消費エネルギーは1万キロカロリー程度に増加しましたが、それでも使用するエネルギーはすべて自然エネルギーでした。19世紀になって蒸気機関やガソリンエンジンを発明し、工業社会が到来しますが、石炭や石油など化石燃料を利用するようになり、そのため使用するエネルギーは7万5000キロカロリーになり、現在では25万キロカロリーを消費して便利な生活をしています。500万年という人類の歴史の最後の0・005%という一瞬のような時間に1人あたり100倍のエネルギーを使って生活しているというのが現代社会です。」要するにエネルギー漬けになっているということである。
産業革命頃の人口が15億人前後ということは、循環型農業で養える人口が15億人前後ということなのであろう。環境問題の根本的解決とは人口を減らす事と、一人当たりのエネルギー使用量を減らす以外に方法はないのである。気候変動が人間の活動によるものかそれとも自然現象によるものかクリアカットな因果関係はまだ不明なのかもしれないが、マイクロプラスチックによる海洋汚染やネオニコチノイド系農薬による昆虫の激減は明らかに人間の責任であろう。現代の環境問題は人間中心主義(ヒューマニズム)が招いた成れの果てなのかも知れない。人間が理解できる範囲内の論理性や合理性といったものが、更に大きな系の中では不合理でしかないということは十分にあり得ることだろう。人間の都合だけで物質循環をいたずらに肥大化させることを止められるかどうかは、今まで築き上げて来た物を手放す事が出来るかどうか、その学び直し(unlearn)が本気で出来るどうかであろう。「気候変動のような大きな問題は楽しく、クールで、セクシーに取り組むべきだ」などといった甘ったるい情緒論で解決できるようなものではない。
ネイティブ・インディアンのホピ族には、物事を選択する時には、7代先の子供たちの事を考えて決めなければならないとい教えがあるそうです。
実話なのか寓話なのか分かりませんが、白人がネイティブ・インディアンに対して、地面に小さな円を描き、これがお前たちが知っている世界だといい、その後その円を包むように大きな円を描きこれが俺達白人の知っている世界だ、だからお前たちは俺達に言う事を聞いていればそれでいいんだと。そうしたら、ネイティブ・インディアンがさらに大きな円を描き、これは白人もインディアンも知らない世界だと。
今、海水温の上昇により海底のメタンハイドレートが融解しメタンガスが大気中に放出されてしまうのではないかということを一部の気象学者が後戻りすることが出来なくなる臨界点として危惧しているそうです。
ケアプランふくしあ 木藤
水洗トイレや蛇口を捻ればお湯が出るという事が当たり前ではないと言われて、そう言われればそうかも知れないと体験的に振り返る事が出来るのは昭和30年代生まれまでだと思う。
このブログをアップするのにも閲覧するにもエネルギーコストが掛かっている。企業から殆ど閲覧されることなく、ただ削除されるだけの莫大なメールがユーザーに送信されている。送信にも削除にもエネルギーコストが掛かっている。(ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、モネロの主要な4種類の仮想通貨のマイニングだけでキューバの使用電力と同じ程度になっていると推計されており、電力消費の限界で仮想通貨は破綻するという予想もあります。:月尾嘉男氏)
日本では、年間2,759万トンの食品廃棄物等が出されている。このうち、まだ食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は643万トン。これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食糧援助量(平成29年で年間約380万トン)の1.7倍に相当します。また、食品ロスを国民一人当たりに換算すると"お茶腕約1杯分(約139g)の食べもの"が毎日捨てられているそうです(農林水産省及び環境省「平成28年度推計」)。食料自給率はカロリーベースでは37%で後の63%は輸入という事である。実質的には何も生みだす事のない食料生産、物流、廃棄にエネルギーだけを消費し経済成長したと喜んでいるのである。昔の常識人であれば、罰当たりと言ったであろう。
物質循環という視点から今の経済活動が抱えている本質的問題を指摘したのは、養老孟司氏(バカの壁)だと思う。樽に入っている酒を八ちゃんと熊ちゃんが互いに酌み交わしながら酒を売買している構図(花見酒)が今の経済活動だと。酒を石油に置き換えたのが現代社会である。この問題を経済の専門家であるアナリスト達が全く指摘しないのは何故なのだろうか?
私たちは炭素循環だけでなく大気中の窒素ガスと水素ガスを反応させてアンモニアを合成させる「ハーバー・ボッシュ法」の開発により窒素循環も大きく変えている。大河内直彦氏によれば、「人類は大量のエネルギーをアンモニア合成につぎ込んでいる。その量は1年間になんと5000兆キロジュールにも達する。これは大型の原発150基分にも相当する莫大な量」という事だそうです。このアンモニアをもとに硫安などの窒素肥料が作られ食料生産が飛躍的に伸び、人口爆発につながっている。化学肥料などがなかった頃の農家が窒素を土に還元するためにどれくらい苦労していたか。昔、水田でレンゲを栽培していたのもマメ科植物と共生する根粒菌による窒素固定を利用したものである。先人の知恵である。
月尾嘉男氏よれば、「人類の歴史を500万年とすると、その99%の期間は狩猟採集生活で、1人の人間が1日に消費するエネルギーは2500キロカロリー程度でした。1万年前くらいに農業を手中にすると、耕作に牛馬を使ったり、灌漑に風車を使ったりするようになり、消費エネルギーは1万キロカロリー程度に増加しましたが、それでも使用するエネルギーはすべて自然エネルギーでした。19世紀になって蒸気機関やガソリンエンジンを発明し、工業社会が到来しますが、石炭や石油など化石燃料を利用するようになり、そのため使用するエネルギーは7万5000キロカロリーになり、現在では25万キロカロリーを消費して便利な生活をしています。500万年という人類の歴史の最後の0・005%という一瞬のような時間に1人あたり100倍のエネルギーを使って生活しているというのが現代社会です。」要するにエネルギー漬けになっているということである。
産業革命頃の人口が15億人前後ということは、循環型農業で養える人口が15億人前後ということなのであろう。環境問題の根本的解決とは人口を減らす事と、一人当たりのエネルギー使用量を減らす以外に方法はないのである。気候変動が人間の活動によるものかそれとも自然現象によるものかクリアカットな因果関係はまだ不明なのかもしれないが、マイクロプラスチックによる海洋汚染やネオニコチノイド系農薬による昆虫の激減は明らかに人間の責任であろう。現代の環境問題は人間中心主義(ヒューマニズム)が招いた成れの果てなのかも知れない。人間が理解できる範囲内の論理性や合理性といったものが、更に大きな系の中では不合理でしかないということは十分にあり得ることだろう。人間の都合だけで物質循環をいたずらに肥大化させることを止められるかどうかは、今まで築き上げて来た物を手放す事が出来るかどうか、その学び直し(unlearn)が本気で出来るどうかであろう。「気候変動のような大きな問題は楽しく、クールで、セクシーに取り組むべきだ」などといった甘ったるい情緒論で解決できるようなものではない。
ネイティブ・インディアンのホピ族には、物事を選択する時には、7代先の子供たちの事を考えて決めなければならないとい教えがあるそうです。
実話なのか寓話なのか分かりませんが、白人がネイティブ・インディアンに対して、地面に小さな円を描き、これがお前たちが知っている世界だといい、その後その円を包むように大きな円を描きこれが俺達白人の知っている世界だ、だからお前たちは俺達に言う事を聞いていればそれでいいんだと。そうしたら、ネイティブ・インディアンがさらに大きな円を描き、これは白人もインディアンも知らない世界だと。
今、海水温の上昇により海底のメタンハイドレートが融解しメタンガスが大気中に放出されてしまうのではないかということを一部の気象学者が後戻りすることが出来なくなる臨界点として危惧しているそうです。
ケアプランふくしあ 木藤
2019年10月31日
秋は短し・・・
ついこの間まで、暑くて暑くて(^-^; 今は朝晩めっきり涼しくというか寒い日もありますね
先日の台風、大雨で怖い思いをされた方、避難を余儀なくされた方などいたのではありませんか?吉川市は、大きな被害はなく済んだようですが、他県の被害状況をテレビで見るたびに胸が痛くなります。我が家でも防災グッズを見直ししました。
話しは変わりますが、先日「たった一言で相手に好かれる魔法の言葉」と言う講座に参加してきました。講師の先生の笑顔がとても印象的で
いい時間を過ごすことが出来ました。その中で私の心に残っていることを少し書こうと思います。
昔は「笑顔」のことを「咲顔」と書いたそうです。
あなたが、目の前の人の為に「笑顔」を花のように咲かせたとき、そのあなたの笑顔に救われる人(仲間)がいるかもしれません。
男性であれ、女性であれ、性別に関係なく、人の笑顔には「まわりの人を元気にする力」があるのですから
私たちの仕事も対人の仕事です。日々利用者様と向き合い、家族様と向き合い、職場の仲間、自分の家族とも
笑顔で接する簡単なようで私はどうだろうと考えてしまいます。
「言葉の魔法」とは?
ネガティブな感情→ポジティブな感情 人は、人から褒められると幸せを感じたりその場の雰囲気がよくなったり、褒められた人も自分に自信が持てるようになったり。
私は実はネガティブな感情の側です。なかなかすぐには自分を変えることも難しいかもしれません。だからなおさら、こんな私でも人から褒められたりするとかなり自信が持てるように思います。褒められることなんてそうそうないとは思いますが、せめて人と接する時は、これからも
「笑顔」で接することを心掛けたいと思います。


ケアプランふくしあ 檜木

先日の台風、大雨で怖い思いをされた方、避難を余儀なくされた方などいたのではありませんか?吉川市は、大きな被害はなく済んだようですが、他県の被害状況をテレビで見るたびに胸が痛くなります。我が家でも防災グッズを見直ししました。
話しは変わりますが、先日「たった一言で相手に好かれる魔法の言葉」と言う講座に参加してきました。講師の先生の笑顔がとても印象的で
いい時間を過ごすことが出来ました。その中で私の心に残っていることを少し書こうと思います。
昔は「笑顔」のことを「咲顔」と書いたそうです。
あなたが、目の前の人の為に「笑顔」を花のように咲かせたとき、そのあなたの笑顔に救われる人(仲間)がいるかもしれません。
男性であれ、女性であれ、性別に関係なく、人の笑顔には「まわりの人を元気にする力」があるのですから

私たちの仕事も対人の仕事です。日々利用者様と向き合い、家族様と向き合い、職場の仲間、自分の家族とも

笑顔で接する簡単なようで私はどうだろうと考えてしまいます。
「言葉の魔法」とは?
ネガティブな感情→ポジティブな感情 人は、人から褒められると幸せを感じたりその場の雰囲気がよくなったり、褒められた人も自分に自信が持てるようになったり。
私は実はネガティブな感情の側です。なかなかすぐには自分を変えることも難しいかもしれません。だからなおさら、こんな私でも人から褒められたりするとかなり自信が持てるように思います。褒められることなんてそうそうないとは思いますが、せめて人と接する時は、これからも
「笑顔」で接することを心掛けたいと思います。



ケアプランふくしあ 檜木
2019年10月18日
セラピューティックケア パート2
以前にもお伝えした”セラピューティックケア”をふくしあの家のご利用者様に受けていただきました。
セラピューティックケアは手の温もりで心に温もりを伝えるケアです。優しく身体に触れるだけで「オキシトシン」という癒しホルモンが分泌され不安やストレスを軽減し安心感や信頼度を高める効果があると言われているものです。初めて受けて下さる皆様は「優しく身体を撫でるだけですよ!」と言ってもどんなことをされるのかと緊張しているのが手のひらを背中に当てた時に感じられます。
それがゆっくり、ゆっくり、手のひら全体で優しくケアを続けていくとだんだんリラックスされてきているのが伝わってきます。
ケアを行う時にはヒーリング音楽をかけ、茶香炉から緑茶の香りを漂わせます。香りや優しい音楽の中でケアを行うと呼吸を整え、α波の活性化を促し、癒しの相乗効果が得られるようです。アロマには色々な良い香りがありますがお茶の香りに癒されるのは日本人だからでしょうか?マッサージ、音楽、香り、どれか一つでも心地よいと感じて頂けたら何よりです 皆様いかがだったでしょうか?
皆様いかがだったでしょうか?
何処でも、いつでもできますので、受けてみたい方は「やって!」と声かけてください
ケアプランふくしあ黒田でした。
セラピューティックケアは手の温もりで心に温もりを伝えるケアです。優しく身体に触れるだけで「オキシトシン」という癒しホルモンが分泌され不安やストレスを軽減し安心感や信頼度を高める効果があると言われているものです。初めて受けて下さる皆様は「優しく身体を撫でるだけですよ!」と言ってもどんなことをされるのかと緊張しているのが手のひらを背中に当てた時に感じられます。
それがゆっくり、ゆっくり、手のひら全体で優しくケアを続けていくとだんだんリラックスされてきているのが伝わってきます。
ケアを行う時にはヒーリング音楽をかけ、茶香炉から緑茶の香りを漂わせます。香りや優しい音楽の中でケアを行うと呼吸を整え、α波の活性化を促し、癒しの相乗効果が得られるようです。アロマには色々な良い香りがありますがお茶の香りに癒されるのは日本人だからでしょうか?マッサージ、音楽、香り、どれか一つでも心地よいと感じて頂けたら何よりです
 皆様いかがだったでしょうか?
皆様いかがだったでしょうか?何処でも、いつでもできますので、受けてみたい方は「やって!」と声かけてください

ケアプランふくしあ黒田でした。
2019年10月09日
施設が置かれている状況
愛知県岡崎市にある社会福祉法人ライトが経営難を理由に静岡市内で経営する三つの特別養護老人ホームの閉鎖を検討しているというニュースがありました。(このような事態が生じることは充分に予見できたことであろうし、恐らく、第2、第3と閉鎖する施設が出てくると思います。)
特養に於ける介護に係る人員基準に「3:1」というものがあります。入所者3人に対して介護職員が1人というものです。この数字だけを見ると充分に介護職員が配置されているように思われるかも知れません。しかし施設は365日24時間稼働しています。1日の労働者の労働時間は8時間です。1週間の内2日は公休日です(5÷7≒0.7)。要するに「9:0.7」、平均すると一人の介護職員で12~13人の入所者を介護することになります。しかも、祝日、有給休暇を一切取得しない条件で。
特養での介護職員の勤務状況は早番、日勤、遅番、夜勤など各施設の状況により勤務シフトを工夫し業務に当たっています。夜勤帯の人員基準は25~30人を1人の介護職員が担当する事になります。ユニット型特養(1ユニット:10人)だと2ユニットを1人の介護職員が担当する事になります。1人でも熱発者がいたり、不穏な人がいると夜勤帯を担当する介護職員はてんてこ舞いする事になります。入所者が60人なら介護職員2人、100名なら4人の介護職員を配置する義務があります。労務管理をする立場にある者からすれば、夜間帯は少人数で対応しなければならないので、能力の低い者同士でペアを組ませることは基本的に避け、比較的能力の高い職員と能力の低い職員をペアにする確率が高くなります。そうすると、能力の高い職員に常に負担がかかる状況が作られ、辞めて欲しくない職員が離職していく可能性が高くなるというジレンマを抱える事になります。
施設入所の相談窓口は、その施設の相談員が受け付ける事になります。もともと、相談員に配置される人ですから、基本的に愛想が良い人が殆どです。ですから、施設入所の相談に行って、窓口になってくれた人が愛想がいいからといってその施設がいいとは限りません。新しい施設はきれいですが、建物が介護する訳でもありません。また、臭いがする施設は良くないと言われる事がありますが、たまたま、オムツ交換の時間帯に施設を見学した場合には、どうしても臭いはあります。介護職員を募集してもなかなか人は来てくれません。他に働くところがなくて応募してくる人が多いという実態もあります。
今の介護施設の置かれている状況で、”良い施設“を探すというのはあまり現実的ではないように思います。”酷い施設(某損保系列のベランダから高齢者を放り投げるような施設や、暴行が横行するような施設等)“を見分けるという意識を持つことの方が大切だと思います。
一つの指標として、実際にケアに当たっている職員たちの表情が能面のような場合には、私なら自分の親をその施設に入所させる事はないと思います。
ケアプランふくしあ 木藤
特養に於ける介護に係る人員基準に「3:1」というものがあります。入所者3人に対して介護職員が1人というものです。この数字だけを見ると充分に介護職員が配置されているように思われるかも知れません。しかし施設は365日24時間稼働しています。1日の労働者の労働時間は8時間です。1週間の内2日は公休日です(5÷7≒0.7)。要するに「9:0.7」、平均すると一人の介護職員で12~13人の入所者を介護することになります。しかも、祝日、有給休暇を一切取得しない条件で。
特養での介護職員の勤務状況は早番、日勤、遅番、夜勤など各施設の状況により勤務シフトを工夫し業務に当たっています。夜勤帯の人員基準は25~30人を1人の介護職員が担当する事になります。ユニット型特養(1ユニット:10人)だと2ユニットを1人の介護職員が担当する事になります。1人でも熱発者がいたり、不穏な人がいると夜勤帯を担当する介護職員はてんてこ舞いする事になります。入所者が60人なら介護職員2人、100名なら4人の介護職員を配置する義務があります。労務管理をする立場にある者からすれば、夜間帯は少人数で対応しなければならないので、能力の低い者同士でペアを組ませることは基本的に避け、比較的能力の高い職員と能力の低い職員をペアにする確率が高くなります。そうすると、能力の高い職員に常に負担がかかる状況が作られ、辞めて欲しくない職員が離職していく可能性が高くなるというジレンマを抱える事になります。
施設入所の相談窓口は、その施設の相談員が受け付ける事になります。もともと、相談員に配置される人ですから、基本的に愛想が良い人が殆どです。ですから、施設入所の相談に行って、窓口になってくれた人が愛想がいいからといってその施設がいいとは限りません。新しい施設はきれいですが、建物が介護する訳でもありません。また、臭いがする施設は良くないと言われる事がありますが、たまたま、オムツ交換の時間帯に施設を見学した場合には、どうしても臭いはあります。介護職員を募集してもなかなか人は来てくれません。他に働くところがなくて応募してくる人が多いという実態もあります。
今の介護施設の置かれている状況で、”良い施設“を探すというのはあまり現実的ではないように思います。”酷い施設(某損保系列のベランダから高齢者を放り投げるような施設や、暴行が横行するような施設等)“を見分けるという意識を持つことの方が大切だと思います。
一つの指標として、実際にケアに当たっている職員たちの表情が能面のような場合には、私なら自分の親をその施設に入所させる事はないと思います。
ケアプランふくしあ 木藤
2019年06月26日
おいーるショック
こんにちは!梅雨の合間の晴れの日です。こんな日は仕事も気持ちよくできます
日々仕事をする中,心掛けていることは、時間を含めた約束
それなのに、あれ?今日は何日?なんて日常茶飯事。
タイトルにも付けましたが(引用)老いはいつの間にか・・・
1日1日を大切に過ごしたいですね。
さて
利用者様と話の中でも良く耳にする中の一つに「骨粗しょう症」があります。
骨粗しょう症とは、エストロゲンが減少した50才以降の女性に多い病気です。
エストロゲンが減少すると、骨の形成と吸収のバランスが崩れ、骨が弱くなります。
伴い、歯や、歯を支える骨も弱くなりますので、骨粗しょう症を患っている人は歯周病が重症化しやすくなると言われています。
また、骨粗しょう症のお薬(BP製剤)を服用していると、抜歯などの外科治療が難しくなります。
先日知り合いの方が、知らずに近くの歯医者へ行き、BP製剤を服用していたことで、
ここでは抜歯ができません。と大学病院を紹介され、松戸まで行くことに
今は無事治療も終わったとの事ですが通院が大変だったと言われていました。

骨粗しょう症予防として食事療法があります。バランスの良い食事を規則的にとるのが基本ですが。
牛乳、小魚、干しエビ、小松菜、青梗菜、大豆製品などの他、
温州ミカンに多く含まれるβークリプトキサンチンが骨粗しょう症のリスクを軽減する効果があるそうです。
これから暑くなります。骨粗しょう症の予防の為だけではなく、暑い夏を乗り切るためにもバランスのいい食事
に心がけ、おいーるショック【老いるショック】も気にせずに頑張っていきましょう

ケアプランふくしあ檜木でした

日々仕事をする中,心掛けていることは、時間を含めた約束
それなのに、あれ?今日は何日?なんて日常茶飯事。
タイトルにも付けましたが(引用)老いはいつの間にか・・・
1日1日を大切に過ごしたいですね。
さて
利用者様と話の中でも良く耳にする中の一つに「骨粗しょう症」があります。
骨粗しょう症とは、エストロゲンが減少した50才以降の女性に多い病気です。
エストロゲンが減少すると、骨の形成と吸収のバランスが崩れ、骨が弱くなります。
伴い、歯や、歯を支える骨も弱くなりますので、骨粗しょう症を患っている人は歯周病が重症化しやすくなると言われています。
また、骨粗しょう症のお薬(BP製剤)を服用していると、抜歯などの外科治療が難しくなります。
先日知り合いの方が、知らずに近くの歯医者へ行き、BP製剤を服用していたことで、
ここでは抜歯ができません。と大学病院を紹介され、松戸まで行くことに

今は無事治療も終わったとの事ですが通院が大変だったと言われていました。
骨粗しょう症予防として食事療法があります。バランスの良い食事を規則的にとるのが基本ですが。
牛乳、小魚、干しエビ、小松菜、青梗菜、大豆製品などの他、
温州ミカンに多く含まれるβークリプトキサンチンが骨粗しょう症のリスクを軽減する効果があるそうです。
これから暑くなります。骨粗しょう症の予防の為だけではなく、暑い夏を乗り切るためにもバランスのいい食事
に心がけ、おいーるショック【老いるショック】も気にせずに頑張っていきましょう


ケアプランふくしあ檜木でした
2019年06月12日
ありがたい
ありがたいの語源である「ありがた・し (有難し)」を岩波古語辞典で引いてみる。
《有ることを欲しても、なかなか困難で実際には少ない、無いの意。稀なことを喜び尊ぶ気持ちから、今日の「ありがたい」という感謝の意に移る》
「有難う」「有難く頂戴します」などの語源である「ありがた・し」とは元々、在る事、存在する事それ自体がかけがえのない尊い事だという感謝の気持ちを表現する言葉である。
小児科医でありかつ自身が小児麻痺である熊谷 晋一郎氏の記事がありました。紹介させて頂きます。
「自立は、依存先を増やすこと、希望は、絶望を分かち合うこと」
“自立”とはどういうことでしょうか?
一般的に「自立」の反対語は「依存」だと勘違いされていますが、人間は物であったり人であったり、さまざまなものに依存しなけと生きていけないんですよ。
東日本大震災のとき、私は職場である5階の研究室から逃げ遅れてしまいました。なぜかというと簡単で、エレベーターが止まってしまったからです。そのとき、逃げるということを可能にする“依存先”が、自分には少なかったことを知りました。エレベーターが止まっても、他の人は階段やはしごで逃げられます。5階から逃げるという行為に対して三つも依存先があります。ところが私にはエレベーターしかなかった。
これが障碍の本質だと思うんです。つまり、“障碍者”というのは、「依存先が限られてしまっている人たち」のこと。健常者は何にも頼らずに自立していて、障碍者はいろいろなものに頼らないと生きていけない人だと勘違いされている。けれども真実は逆で、健常者はさまざまなものに依存できていて、障碍者は限られたものにしか依存できていない。依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くすると、何にも依存してないかのように錯覚できます。“健常者である”というのはまさにそういうことなのです。世の中のほとんどのものが健常者向けにデザインされていて、その便利さに依存している事を忘れているわけです。
何を持って生産性のある人間、生産性のない人間というのであろうか。自立支援とは生産性のある人間が、生産性のない人間を生産性のある人間に変革するということなのだろうか。恐らく、今の社会で言う自立している人間とは、都市化された社会の中で適切な振舞いが取れることと、経済生活が行えていること、この2点をクリアーしている人間のことを言うのであろう。それ以外は生産性に問題のある自立していない支援が必要な人間ということなのだろう。
自己家畜化している都市生活者が一人サバンナに放り出されればなす術もなく死を待つだけだろう。都市生活者の自立とは、エネルギーの大量使用による幾重もの保護膜による守りとそれによって生じる環境負荷という外部不経済性を垂れ流すことによってやっと成り立っているだけである。元々、相互依存の中でしか人は生きられないという当たり前の事を忘れているのは、都市化された社会の中で自立していると錯覚している側の人間なのである。生産性で人を選別する発言をした国会議員と相模原障害者施設殺傷事件を起こした人間は傲慢性に於いて通底している。
ホスピスに勤務されている沼野尚美氏が書かれた「癒されて旅立ちたい」という本の中で妊娠中に癌が判明した若い妊婦さんの事を記述されている所があります。略して紹介させて頂きます。
Sさんは妊娠中に自分が癌にかかっていることを知りました。母親になれる喜びをかみしめながら、生まれてくる赤ちゃんのための準備を進めていたのです。とにかくすべてが初めての経験でしたので、体調が悪いのもつわりのせいと思い込んでいました。やがて、その症状は癌のためであることがわかり、彼女は大きな人生の選択をすることになりました。
医師からは「今、赤ちゃんを堕ろせば、あなた自身の命が長く延びる可能性が高くなります」という説明を彼女は受けました。しかし、与えられた命を守ってやりたいといって、彼女は産むことを決心するのです。自分の体の中に、誕生と死の両方を抱えてまったく迷いがなかったと言えば嘘になるでしょう。しかし、彼女は現実を正しく理解した上で、自分にとってリスクの高い道、お腹の中の赤ちゃんの命を守る道を選びました。
無事に元気な赤ちゃんを出産した後、末期癌患者となった彼女に後悔はないか聞いてみました。「後悔していない」と彼女ははっきりと答えました。ただ、育てていくことのできない悔しさと悲しみ、体力がないためにしっかりと抱きしめてあげられない子供への申し訳なさを、涙ながらに語りました。
「在る事」「存在する事」それ自体が有難く尊いのであ。その事を腹の底から了解できるような人間になれるよう努力して行く事が相互依存の中でしか生きていく事の出来ない人間の自立性なのでなないだろうか。上から目線で金科玉条のように「自立支援」を唱える自立していると錯覚している側の人々の無明に光が届きますように。
ケアプランふくしあ 木藤
《有ることを欲しても、なかなか困難で実際には少ない、無いの意。稀なことを喜び尊ぶ気持ちから、今日の「ありがたい」という感謝の意に移る》
「有難う」「有難く頂戴します」などの語源である「ありがた・し」とは元々、在る事、存在する事それ自体がかけがえのない尊い事だという感謝の気持ちを表現する言葉である。
小児科医でありかつ自身が小児麻痺である熊谷 晋一郎氏の記事がありました。紹介させて頂きます。
「自立は、依存先を増やすこと、希望は、絶望を分かち合うこと」
“自立”とはどういうことでしょうか?
一般的に「自立」の反対語は「依存」だと勘違いされていますが、人間は物であったり人であったり、さまざまなものに依存しなけと生きていけないんですよ。
東日本大震災のとき、私は職場である5階の研究室から逃げ遅れてしまいました。なぜかというと簡単で、エレベーターが止まってしまったからです。そのとき、逃げるということを可能にする“依存先”が、自分には少なかったことを知りました。エレベーターが止まっても、他の人は階段やはしごで逃げられます。5階から逃げるという行為に対して三つも依存先があります。ところが私にはエレベーターしかなかった。
これが障碍の本質だと思うんです。つまり、“障碍者”というのは、「依存先が限られてしまっている人たち」のこと。健常者は何にも頼らずに自立していて、障碍者はいろいろなものに頼らないと生きていけない人だと勘違いされている。けれども真実は逆で、健常者はさまざまなものに依存できていて、障碍者は限られたものにしか依存できていない。依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くすると、何にも依存してないかのように錯覚できます。“健常者である”というのはまさにそういうことなのです。世の中のほとんどのものが健常者向けにデザインされていて、その便利さに依存している事を忘れているわけです。
何を持って生産性のある人間、生産性のない人間というのであろうか。自立支援とは生産性のある人間が、生産性のない人間を生産性のある人間に変革するということなのだろうか。恐らく、今の社会で言う自立している人間とは、都市化された社会の中で適切な振舞いが取れることと、経済生活が行えていること、この2点をクリアーしている人間のことを言うのであろう。それ以外は生産性に問題のある自立していない支援が必要な人間ということなのだろう。
自己家畜化している都市生活者が一人サバンナに放り出されればなす術もなく死を待つだけだろう。都市生活者の自立とは、エネルギーの大量使用による幾重もの保護膜による守りとそれによって生じる環境負荷という外部不経済性を垂れ流すことによってやっと成り立っているだけである。元々、相互依存の中でしか人は生きられないという当たり前の事を忘れているのは、都市化された社会の中で自立していると錯覚している側の人間なのである。生産性で人を選別する発言をした国会議員と相模原障害者施設殺傷事件を起こした人間は傲慢性に於いて通底している。
ホスピスに勤務されている沼野尚美氏が書かれた「癒されて旅立ちたい」という本の中で妊娠中に癌が判明した若い妊婦さんの事を記述されている所があります。略して紹介させて頂きます。
Sさんは妊娠中に自分が癌にかかっていることを知りました。母親になれる喜びをかみしめながら、生まれてくる赤ちゃんのための準備を進めていたのです。とにかくすべてが初めての経験でしたので、体調が悪いのもつわりのせいと思い込んでいました。やがて、その症状は癌のためであることがわかり、彼女は大きな人生の選択をすることになりました。
医師からは「今、赤ちゃんを堕ろせば、あなた自身の命が長く延びる可能性が高くなります」という説明を彼女は受けました。しかし、与えられた命を守ってやりたいといって、彼女は産むことを決心するのです。自分の体の中に、誕生と死の両方を抱えてまったく迷いがなかったと言えば嘘になるでしょう。しかし、彼女は現実を正しく理解した上で、自分にとってリスクの高い道、お腹の中の赤ちゃんの命を守る道を選びました。
無事に元気な赤ちゃんを出産した後、末期癌患者となった彼女に後悔はないか聞いてみました。「後悔していない」と彼女ははっきりと答えました。ただ、育てていくことのできない悔しさと悲しみ、体力がないためにしっかりと抱きしめてあげられない子供への申し訳なさを、涙ながらに語りました。
「在る事」「存在する事」それ自体が有難く尊いのであ。その事を腹の底から了解できるような人間になれるよう努力して行く事が相互依存の中でしか生きていく事の出来ない人間の自立性なのでなないだろうか。上から目線で金科玉条のように「自立支援」を唱える自立していると錯覚している側の人々の無明に光が届きますように。
ケアプランふくしあ 木藤