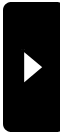› 介護の「ふくしあ」-スタッフブログ › ケアプランふくしあ-居宅介護支援
2022年03月15日
人生会議(アドバンス・ケア・プランニング)
「人生会議」とは、アドバンス・ケア・ プランニング(Advance Care Planning)の愛称(?)だそうです。医師会ではACPを、将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、本人を主体に、そのご家族や近しい人、医療・ケアチームが、繰り返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援するプロセスであると定義されています。その人生会議を国が主導するというのは、その背後にこれから多死社会を迎える焦りのようなものがあるのだろうか。
モンテーニューがエッセーに老衰による死を次のように書いている。「老衰による死はまれかつ単独に起こる例外的な死である、他の死と比べるととても不自然なことだ。それは死に方の中でも最終的で極端なものだ」と。16世紀末のワクチンも細菌学も抗生物質もなかった時代では殆どの人が老衰前に亡くなっていたということなのだろう。
皮肉なものである。医療が発達したおかげで多くの人が長生きするようになり、かつてイヴァン・イリイチが指摘したように社会保障に対する依存度の増大がそれに対する税金負担がどのような経済でも支えきれないほど増えたことに、社会全体が圧迫感を感じているのだろう。だから治療とはそもそも延命させる為に行っているのであって、短命にしようと思って行っている訳ではないのに、特に高齢者の終末期治療を延命治療と、敢えて”延命“という枕詞を添えるのはどこか“無駄な治療”という気持ちを多くの人が持っているという事なのだろう。本人、家族、治療者にとっても不幸な事だと思う。医療的な介入が本人にとってどのような意味があるのかを、医療的介入の適合期、拮抗期、過介入期などといったステージで表現していく工夫があってもいいような気がする。その方がACPを考える上で足掛かりになるのではないかと思う。
人はいずれ皆死ぬ。人は死に各々どのような態度で向き合っていくのであろうか。高村光太郎のように「死ねば死にきり 自然は水際たっている」という言い切りが出来るかと言えば、私の場合何か未練が残るし、かといってキリスト教的な永遠の生命などというのは鬱陶しいし、絶対苦の中で展開される輪廻転生というループから脱却するために、あらゆる執着を断ち切って行くという仏教的な境地を獲得することは到底出来ないし、困ったものである。私の個人的嗜好としては「人間は死ねば、精霊として天上で生き、その後再び男はハエ、アリ、女はダニ、ノミとなり虫として地上に戻りそして最後は消えて行く」というアマゾンの未開の地で暮らすヤノマミ族の死生観が好きである。現代人として自然界からありとあらゆるものを収奪し生き死んだ者として天上界で少し猶予を頂き、その後、シロアリとして地上に戻り生態系の下部構造としてセルロースをせっせと分解し土に還元し自然のお役に立って消えていくというのはなかなか据わりがいい。
谷川俊太郎氏が母親の介護について、対談の中で次のように語っている。「僕は、100%人間は行き続けるほうがいいのだとは、言いきれない気もするのです。90歳までいろいろな病気を克服して、しかも色々な人に介護してもらって生きているというのは、昔の考え方でいうと、神とか宿命とか言われるものを人工的に拒否している面があるように、僕には見えるのです。僕の母は4年7ヶ月ベッドの上で挿管されて、話も何もできない状態でした。感情を読み取っても全然頼りないし、そういうのを見ていると、死んで欲しいという気持もある。解決のつかない矛盾をずっと自分のなかで保っていくしかない、というのかな。そんな気がします。」
西行は、「ねがはくは花の下にて春死なん そのきさらぎの望月のころ」という自分の歌のとおりにその願いを遂げて死んだそうである。それは、当時の修行者たちは、命がそろそろ尽きそうになることを感じた段階で、緩やかに木食に入り、そして断食に入って自分の死期というものをある程度、調整していたという事である。
文化人類学者の原ひろ子氏が『ヘヤー・インディアンとその世界』という書物に、カナダの北方地方に住むヘヤー・インディアンの人たちがどのように死を受け止めるかが語られていて、「ヘヤー・インディアンは何のために生きているのだろうか。美しい死に顔で死ぬために生きているのだ」とある。ヘヤー・インディアンは各人が心のなかに「守護霊」をもっていて、何かにつけてその守護霊と「話しあい」をしている。年老いて病気になったとき、守護霊が「おまえは死ぬ」と言うとそれに従い、親族を集めて、思い出話などをし、絶食して死を待つのである。そして、守護霊に助けを求めて「よい顔で死ねるように」願うそうである。
現代を生きる私たちがこれをそのまま受け入れることはできないが、「よい顔で死ねるように」という切り口は、ターミナルに関わる周囲の者たちにとっても一つの希望になるのではないだろうか。「地」と「図」を反転させれば「よい顔で生ききれるように」と言ってもいいと思う。ただ、そのように望んだとしても病気によってはそのようなゆとりが持てないケースも多々ある事も事実だろう。
どのように死と向き合うのかというような重い意味を持つ外来語(ACP)を翻訳する時はできれば和語に変換する方が心情に響くと思う。
「よい顔で死ねるように」―お迎えに向けた身仕舞を語り合おう―如何せん和語は名詞化する力が弱いのでどうしても冗長的になってしまう。私の精一杯である。和語にこだわらなければ、アルフォンス・デーケンが提唱していた「死への準備教育」とか、大井玄氏が『人間の往生』の中で「医療技術による管理が進めば進むほど、死は家族から隠される傾向にある。死は、家族、そして社会一般から隔離され、抽象化され、結果としてほとんど神経症的に怖れられる現象となった」と指摘しているように、そのような社会的状況を打破するために「死に方の選択」のような直截的な翻訳でも良いような気もする。
江戸から明治への移行期を生きた教養人の漢字に対する素養は現代人を遥かに凌駕していただろう。福沢諭吉や西周らであったならば、Advance Care Planningをどのように漢字に変換しであろうか。言語明瞭意味不明な「人生会議」にはならなかったような気がする。どなたか言語センスの高い人に「和語」に「漢語」に変換して頂けたらと思う。
ケアプランふくしあ 木藤
モンテーニューがエッセーに老衰による死を次のように書いている。「老衰による死はまれかつ単独に起こる例外的な死である、他の死と比べるととても不自然なことだ。それは死に方の中でも最終的で極端なものだ」と。16世紀末のワクチンも細菌学も抗生物質もなかった時代では殆どの人が老衰前に亡くなっていたということなのだろう。
皮肉なものである。医療が発達したおかげで多くの人が長生きするようになり、かつてイヴァン・イリイチが指摘したように社会保障に対する依存度の増大がそれに対する税金負担がどのような経済でも支えきれないほど増えたことに、社会全体が圧迫感を感じているのだろう。だから治療とはそもそも延命させる為に行っているのであって、短命にしようと思って行っている訳ではないのに、特に高齢者の終末期治療を延命治療と、敢えて”延命“という枕詞を添えるのはどこか“無駄な治療”という気持ちを多くの人が持っているという事なのだろう。本人、家族、治療者にとっても不幸な事だと思う。医療的な介入が本人にとってどのような意味があるのかを、医療的介入の適合期、拮抗期、過介入期などといったステージで表現していく工夫があってもいいような気がする。その方がACPを考える上で足掛かりになるのではないかと思う。
人はいずれ皆死ぬ。人は死に各々どのような態度で向き合っていくのであろうか。高村光太郎のように「死ねば死にきり 自然は水際たっている」という言い切りが出来るかと言えば、私の場合何か未練が残るし、かといってキリスト教的な永遠の生命などというのは鬱陶しいし、絶対苦の中で展開される輪廻転生というループから脱却するために、あらゆる執着を断ち切って行くという仏教的な境地を獲得することは到底出来ないし、困ったものである。私の個人的嗜好としては「人間は死ねば、精霊として天上で生き、その後再び男はハエ、アリ、女はダニ、ノミとなり虫として地上に戻りそして最後は消えて行く」というアマゾンの未開の地で暮らすヤノマミ族の死生観が好きである。現代人として自然界からありとあらゆるものを収奪し生き死んだ者として天上界で少し猶予を頂き、その後、シロアリとして地上に戻り生態系の下部構造としてセルロースをせっせと分解し土に還元し自然のお役に立って消えていくというのはなかなか据わりがいい。
谷川俊太郎氏が母親の介護について、対談の中で次のように語っている。「僕は、100%人間は行き続けるほうがいいのだとは、言いきれない気もするのです。90歳までいろいろな病気を克服して、しかも色々な人に介護してもらって生きているというのは、昔の考え方でいうと、神とか宿命とか言われるものを人工的に拒否している面があるように、僕には見えるのです。僕の母は4年7ヶ月ベッドの上で挿管されて、話も何もできない状態でした。感情を読み取っても全然頼りないし、そういうのを見ていると、死んで欲しいという気持もある。解決のつかない矛盾をずっと自分のなかで保っていくしかない、というのかな。そんな気がします。」
西行は、「ねがはくは花の下にて春死なん そのきさらぎの望月のころ」という自分の歌のとおりにその願いを遂げて死んだそうである。それは、当時の修行者たちは、命がそろそろ尽きそうになることを感じた段階で、緩やかに木食に入り、そして断食に入って自分の死期というものをある程度、調整していたという事である。
文化人類学者の原ひろ子氏が『ヘヤー・インディアンとその世界』という書物に、カナダの北方地方に住むヘヤー・インディアンの人たちがどのように死を受け止めるかが語られていて、「ヘヤー・インディアンは何のために生きているのだろうか。美しい死に顔で死ぬために生きているのだ」とある。ヘヤー・インディアンは各人が心のなかに「守護霊」をもっていて、何かにつけてその守護霊と「話しあい」をしている。年老いて病気になったとき、守護霊が「おまえは死ぬ」と言うとそれに従い、親族を集めて、思い出話などをし、絶食して死を待つのである。そして、守護霊に助けを求めて「よい顔で死ねるように」願うそうである。
現代を生きる私たちがこれをそのまま受け入れることはできないが、「よい顔で死ねるように」という切り口は、ターミナルに関わる周囲の者たちにとっても一つの希望になるのではないだろうか。「地」と「図」を反転させれば「よい顔で生ききれるように」と言ってもいいと思う。ただ、そのように望んだとしても病気によってはそのようなゆとりが持てないケースも多々ある事も事実だろう。
どのように死と向き合うのかというような重い意味を持つ外来語(ACP)を翻訳する時はできれば和語に変換する方が心情に響くと思う。
「よい顔で死ねるように」―お迎えに向けた身仕舞を語り合おう―如何せん和語は名詞化する力が弱いのでどうしても冗長的になってしまう。私の精一杯である。和語にこだわらなければ、アルフォンス・デーケンが提唱していた「死への準備教育」とか、大井玄氏が『人間の往生』の中で「医療技術による管理が進めば進むほど、死は家族から隠される傾向にある。死は、家族、そして社会一般から隔離され、抽象化され、結果としてほとんど神経症的に怖れられる現象となった」と指摘しているように、そのような社会的状況を打破するために「死に方の選択」のような直截的な翻訳でも良いような気もする。
江戸から明治への移行期を生きた教養人の漢字に対する素養は現代人を遥かに凌駕していただろう。福沢諭吉や西周らであったならば、Advance Care Planningをどのように漢字に変換しであろうか。言語明瞭意味不明な「人生会議」にはならなかったような気がする。どなたか言語センスの高い人に「和語」に「漢語」に変換して頂けたらと思う。
ケアプランふくしあ 木藤
2021年10月21日
保育・介護に関わる産業を冷遇し続ける社会
現在、日本人の平均年齢は約47歳だそうです。いわゆる団塊ジュニア世代です。総務省の年代別の人口集計を参考に1972年産まれを100として比率を産出すると1980年で80%を、1986年で70%を、2001年で60%を、2014年に50%を下回っています。2019年は45.04%となっています。新型コロナウイルスの問題で少子化はさらに加速されていると思います。日本社会の問題は高齢化よりも少子化の方が重大問題でしょう。
1989年に出版された「河合隼雄全対話3 父性原理と母性原理」の中で鶴見俊輔と次のような対話をしている部分がある。
『鶴見 ― もうひとつこの本のテーマは老年ですね。
老いて死んでいくとき、そばにいてくれるものとしては女性がいい。女性のほうが死にゆくものの看取りがよくできる。これは女性の光栄というか、たいへんなことですよね。男性社会でそれを悪く利用されて、寝たきり老人の九割は女性が世話している。しかも無償で。それに対して私たちは評価しなきゃいけない。経済的な裏付けをしなきゃいけない。
河合 ― 全くそうです。彼女がすごく評価していることが、実際は経済的に実に低く評価されている。アメリカという国では、男性的といわれる仕事のほうは経済的価値が高すぎる。死んでいく人のそばにいてくれる人にはものすごいお金を払っていいはずですよ。そうでしょ、元気なとき、ワッショイ、ワッショイって神輿かついでくれる人なんかには金はいらんですよ。静かに死ねるためにほんとにハタにおった女性なんてのはすごく価値があるんです。ところが経済的には低い。
ここでひとつ言えるのは、そのような仕事は、以前は金で買えないものだからという考えもあったのじゃないか。金で買えない大事なことに、お金をあげるなって非常に失礼だという感じ方ですね。ところがいまのわれわれの社会の中では、経済的価値でものごとを見る。そういうふうに考えると、女性原理に基づく仕事に対する報酬という問題は非常に重要だと思いますね。そこで気の毒なのは、女性原理の仕事をしていれば非常に安定している女性が、ムリに男性原理の仕事をしてそれに向いていないというとき、ごく少ない金にしかならない。深く考えるべき問題があります。』
日本が工業化していく過程で原発は経済成長の要だという意識が政府、経団連には強くあったはずである。エネルギー問題は国の存亡に直結するだけに、電力関連の産業を電源三法で手厚く保護し、そして一基の原発だけでも何千億というお金が動く原発事業には巨大な利権が絡み続けているのだろう。
福島原発について大沼安史は次のように言っている。東電の「廃炉に向けた『中長期』ロードマップ」によると、「フクイチ廃炉」は遅くとも2051年に完了することになっている。もちろん、これは「スーパーヒーロー」級の廃炉ロボットが現れるので技術的なブレークスルーがあっての話で、いまのところ「空想」に過ぎないが、かりのその時点で全てが終わるにせよ、投入される「人材」は1日5千人ペースが続くとして、延べ約6千万人に達する。フクイチの現場は、日本人はもちろん人類としても初めて経験する、人間の労働を際限なく吸い込み続ける巨大なブラックホールである。
小熊英二氏によれば、『高速増殖炉「もんじゅ」は1日5千万円とも言われる費用を投じながら動かせていません。(1兆2千億円以上の費用を投じてきた「もんじゅ」は2018年3月に廃炉が確定。これから3,750億円を投じ30年かけて廃炉にするとの事だが技術的な目途は全く立っていない。— 技術的な目途が立っていないのに何故、費用が算定できるのだろうか?— )青森県六ヶ所村の使用済み核燃料再処理施設は、1993年から建設を開始しましたが、当初予定の3倍近い2兆2千億円を費やしても技術的問題が解決せず、1日3億円とも言われる維持費をからながら本格運転できないでいます。』実質的に何も生み出さないどころか、負の遺産にしかならない物にこれだけのコストをかけ続けてもいわゆる原子力村を保護し続けているのである。そして、核燃リサイクルという虚構が破綻し行き場を失った放射性廃棄物を政府は地層処分しようとしています。
私達の住む日本の地球上に占める陸地面積の比率は0.25%です。4つのプレートがひしめき合う地震の多発地帯です。また、世界の活火山(1548)の7%(108)が日本にあるそうです。これが私達の住む地球上0.25%の陸地の地質的条件です。このような条件において原子力発電所を推進していくこと自体大きな問題を孕んでいると思います。かつて、原発推進派は安全性において地震で原発にトラブルが発生することはないといっていました。いざ実際に被害が発生すると「想定外の地震」と言います。原発稼動にともなう放射性廃棄物について、半減期が二万年以上のプルトニウムを含む高レベル放射性廃棄物を、政府は「深地層処分」する方針で、原子力発電環境整備機構の自作自演的Q&Aによると「なぜ地上での管理ではなく地下に処分するの?」という質問に対して、答えを要約すれば「管理を続けなければ安全が保てないようなシステムであってはいけない」だから、安定した「深地層部」に高レベル廃棄物を埋めるということです。極めて官僚的な詭弁的論法です。この人達は何ら実質的責任を負いません。いざ問題が発生すれば、「想定外でした」以上、お仕舞、でしょう。先に書いたように数万年の時間スケールで日本に安定な地層がそもそもあるのでしょうか。
工業化を推進してきた産業界は自分達が日本経済を牽引してきたと思っているのだろう。確かに山を築きて来たのだろう。だが、原発に象徴されるようエネルギーを大量に使用する産業は、せっせと深い谷を将来世代に注入して現在の山を成り立たせているだけではないのか。
乳幼児期に情緒的安定性の高い大人に保育されることが、その子の将来にとってどれだけ大切なことか。保育とは誰にでもできる簡単な仕事なのだろうか。
老いて人の手助けが必要になった時、人の痛みに対して深い洞察力のある人に介護されるのとそうでないとの違いが想像できるだろうか。フィジカル面に於いても、メンタル面に於いても高い見識を持ち、かつ、人の痛みに対して深い洞察力のある介護士であったならば、年収が1500万円以上であってもおかしくはないと思う。
岸田首相は保育・介護従事者の処遇を改善すると言っているが、所詮、選挙前のリップサービスでしょう。日本社会の価値選択の総和としての統治体質に於いて少子化が進むのは必然のように思う。早晩、出生数が80万人(40%未満)を下回るだろう。
ケアプランふくしあ 木藤
1989年に出版された「河合隼雄全対話3 父性原理と母性原理」の中で鶴見俊輔と次のような対話をしている部分がある。
『鶴見 ― もうひとつこの本のテーマは老年ですね。
老いて死んでいくとき、そばにいてくれるものとしては女性がいい。女性のほうが死にゆくものの看取りがよくできる。これは女性の光栄というか、たいへんなことですよね。男性社会でそれを悪く利用されて、寝たきり老人の九割は女性が世話している。しかも無償で。それに対して私たちは評価しなきゃいけない。経済的な裏付けをしなきゃいけない。
河合 ― 全くそうです。彼女がすごく評価していることが、実際は経済的に実に低く評価されている。アメリカという国では、男性的といわれる仕事のほうは経済的価値が高すぎる。死んでいく人のそばにいてくれる人にはものすごいお金を払っていいはずですよ。そうでしょ、元気なとき、ワッショイ、ワッショイって神輿かついでくれる人なんかには金はいらんですよ。静かに死ねるためにほんとにハタにおった女性なんてのはすごく価値があるんです。ところが経済的には低い。
ここでひとつ言えるのは、そのような仕事は、以前は金で買えないものだからという考えもあったのじゃないか。金で買えない大事なことに、お金をあげるなって非常に失礼だという感じ方ですね。ところがいまのわれわれの社会の中では、経済的価値でものごとを見る。そういうふうに考えると、女性原理に基づく仕事に対する報酬という問題は非常に重要だと思いますね。そこで気の毒なのは、女性原理の仕事をしていれば非常に安定している女性が、ムリに男性原理の仕事をしてそれに向いていないというとき、ごく少ない金にしかならない。深く考えるべき問題があります。』
日本が工業化していく過程で原発は経済成長の要だという意識が政府、経団連には強くあったはずである。エネルギー問題は国の存亡に直結するだけに、電力関連の産業を電源三法で手厚く保護し、そして一基の原発だけでも何千億というお金が動く原発事業には巨大な利権が絡み続けているのだろう。
福島原発について大沼安史は次のように言っている。東電の「廃炉に向けた『中長期』ロードマップ」によると、「フクイチ廃炉」は遅くとも2051年に完了することになっている。もちろん、これは「スーパーヒーロー」級の廃炉ロボットが現れるので技術的なブレークスルーがあっての話で、いまのところ「空想」に過ぎないが、かりのその時点で全てが終わるにせよ、投入される「人材」は1日5千人ペースが続くとして、延べ約6千万人に達する。フクイチの現場は、日本人はもちろん人類としても初めて経験する、人間の労働を際限なく吸い込み続ける巨大なブラックホールである。
小熊英二氏によれば、『高速増殖炉「もんじゅ」は1日5千万円とも言われる費用を投じながら動かせていません。(1兆2千億円以上の費用を投じてきた「もんじゅ」は2018年3月に廃炉が確定。これから3,750億円を投じ30年かけて廃炉にするとの事だが技術的な目途は全く立っていない。— 技術的な目途が立っていないのに何故、費用が算定できるのだろうか?— )青森県六ヶ所村の使用済み核燃料再処理施設は、1993年から建設を開始しましたが、当初予定の3倍近い2兆2千億円を費やしても技術的問題が解決せず、1日3億円とも言われる維持費をからながら本格運転できないでいます。』実質的に何も生み出さないどころか、負の遺産にしかならない物にこれだけのコストをかけ続けてもいわゆる原子力村を保護し続けているのである。そして、核燃リサイクルという虚構が破綻し行き場を失った放射性廃棄物を政府は地層処分しようとしています。
私達の住む日本の地球上に占める陸地面積の比率は0.25%です。4つのプレートがひしめき合う地震の多発地帯です。また、世界の活火山(1548)の7%(108)が日本にあるそうです。これが私達の住む地球上0.25%の陸地の地質的条件です。このような条件において原子力発電所を推進していくこと自体大きな問題を孕んでいると思います。かつて、原発推進派は安全性において地震で原発にトラブルが発生することはないといっていました。いざ実際に被害が発生すると「想定外の地震」と言います。原発稼動にともなう放射性廃棄物について、半減期が二万年以上のプルトニウムを含む高レベル放射性廃棄物を、政府は「深地層処分」する方針で、原子力発電環境整備機構の自作自演的Q&Aによると「なぜ地上での管理ではなく地下に処分するの?」という質問に対して、答えを要約すれば「管理を続けなければ安全が保てないようなシステムであってはいけない」だから、安定した「深地層部」に高レベル廃棄物を埋めるということです。極めて官僚的な詭弁的論法です。この人達は何ら実質的責任を負いません。いざ問題が発生すれば、「想定外でした」以上、お仕舞、でしょう。先に書いたように数万年の時間スケールで日本に安定な地層がそもそもあるのでしょうか。
工業化を推進してきた産業界は自分達が日本経済を牽引してきたと思っているのだろう。確かに山を築きて来たのだろう。だが、原発に象徴されるようエネルギーを大量に使用する産業は、せっせと深い谷を将来世代に注入して現在の山を成り立たせているだけではないのか。
乳幼児期に情緒的安定性の高い大人に保育されることが、その子の将来にとってどれだけ大切なことか。保育とは誰にでもできる簡単な仕事なのだろうか。
老いて人の手助けが必要になった時、人の痛みに対して深い洞察力のある人に介護されるのとそうでないとの違いが想像できるだろうか。フィジカル面に於いても、メンタル面に於いても高い見識を持ち、かつ、人の痛みに対して深い洞察力のある介護士であったならば、年収が1500万円以上であってもおかしくはないと思う。
岸田首相は保育・介護従事者の処遇を改善すると言っているが、所詮、選挙前のリップサービスでしょう。日本社会の価値選択の総和としての統治体質に於いて少子化が進むのは必然のように思う。早晩、出生数が80万人(40%未満)を下回るだろう。
ケアプランふくしあ 木藤
2021年08月13日
大人の能力(努力の方向性)
ケアマネジャーという資格は更新制ということもあり比較的研修の多い職種です。国が目指す地域包括ケアシステムが上手く機能していないのは個々のケアマネジャーの能力が低いからだとの事で、その底上げをする必要があると考えているようです。しかし、いい歳になった私は研修をすれば能力が向上するという考えを今一つ信用することが出来ない。
能力というものを三角形的にイメージし、底辺を資質、努力を垂直方向へのベクトルとして、それを面積として考えた場合、仮に資質10の者が2努力した場合、能力は10である。資質1の者が20努力した場合、能力は10である。だが、努力すれば報われるというのは限られた範囲の中での話で現実はそれ程甘くはない。底辺が大きくなければ、いくら努力を積み上げても高さも形成されない。身体動作を伴うスポーツを考えれば明白である。日本人の場合どんなに努力しても100mを9秒台で走れた人間は4人(そのうち一人はハーフ)だけである。資質の無い者がどんなに努力しても能力が高まることはない。それどころかスポーツマンやピヤニストなど資質のある者が努力のし過ぎでイップスやジストニアを発症し、資質が台無しになってしまう事もあるのである。
幼児が母語を習得していく過程で努力感はあまりないと思う。何かの能力を習得していく過程で努力感が募ってくるのは恐らく、資質上の限界点が見えて来ているという事だろう。真正の能力向上は努力感が苦にならない(充実感に満ちている)時に形成されるもののように思う。多くの日本人が中高生という生物学的には成長期にある時期に英語を学習しても実用レベルまで習得することができないのは、言語習得という資質に関しては10代半ばで既に減衰してしまっているという事だろう。
垂直方向での能力の向上は生物学的成長がほぼ完成する二十歳前後までに形成されたものがその人のベースで、それがその後の人生で上昇したとしてもごくわずかだと思う。成長後の大人に要求されるのは経験による成熟という水平方向的な広がり、イメージとしては三角形的なものから台形的になって行く感じだろうか。その者の持つベースに応じたレベルで、いろいろと経験し幅が広がって行き社会的能力が身に付いていく訳で、常識的に考えれば能力差は広がる事はあっても縮むことは無い。
坂東玉三郎が以前、師匠から受ける注意は一回だけ、その時その注意の意味を理解できなかったとき二度と注意はしてくれませんと、言っていたがそれが大人の指導というものだろう。厳しさというより合理的判断なのである。注意の内容の重要性を感じ取る資質が受け手に無い場合、いくら注意しても時間の無駄なのである。要するに資質がないのである。自分の資質に応じた範囲内でしか人は成長できい。それだけの事である。(逆も真で、自分の資質を超えて人を指導することは出来ない。指導される側の資質が勝っている場合、指導者にそれを受け入れる度量がないと、威圧という手段をとることになる。)
中年以降に能力向上の伸びしろなどないであろう。中高年を対象とした能力開発などと言ったものはフィクションであって、現実には能力の減衰が始まっている。もはや指導の対象者ではないのである。自然は冷徹である。中高年に必要なのは能力向上にむけた無駄な努力ではなく、どの様に自分自身を経年変化させていくかだと思う。自分を変えられるのは自分だけである。私が思うに中高年以降に大切なのは心を如何にしなやかにして行けるかだと思う。社会的成功を収めても晩年になって重度の心の硬化を発症し人間的にはまったく魅力のない高齢者もいれば、例え認知症になっても人間的に魅力的な高齢者も結構いるものである。
心をしなやかにしていくにはどうすればいいのか。「初々しさが大切なの 人に対しても世の中に対しても 人を人とも思わなくなったとき堕落が始まるのね」という茨木のり子の言葉が示唆に富んでいると思う。「自分を大切にするように、隣人を大切にせよ」「たとえ敵対する相手でも人として大事にしろ」というマルコの言葉を思い出す。人は人を人と思うレベルに応じて人格が陶冶され、人は人を人と思わなくなるレベルに応じて心が硬化し醜悪になって行く。
中高年になり若い時に比べ不機嫌になることが増えたり、他人を許容できなくなってきた場合には、自分の能力以上の事に手を出し過ぎていないかどうか、自分の生き方に何か問題がなかどうか、自分自身の退行から眼を逸らさず冷静に見つめ直す必要があると思う。人を人と思うゆとりを失わない為に。
ケアプランふくしあ 木藤
能力というものを三角形的にイメージし、底辺を資質、努力を垂直方向へのベクトルとして、それを面積として考えた場合、仮に資質10の者が2努力した場合、能力は10である。資質1の者が20努力した場合、能力は10である。だが、努力すれば報われるというのは限られた範囲の中での話で現実はそれ程甘くはない。底辺が大きくなければ、いくら努力を積み上げても高さも形成されない。身体動作を伴うスポーツを考えれば明白である。日本人の場合どんなに努力しても100mを9秒台で走れた人間は4人(そのうち一人はハーフ)だけである。資質の無い者がどんなに努力しても能力が高まることはない。それどころかスポーツマンやピヤニストなど資質のある者が努力のし過ぎでイップスやジストニアを発症し、資質が台無しになってしまう事もあるのである。
幼児が母語を習得していく過程で努力感はあまりないと思う。何かの能力を習得していく過程で努力感が募ってくるのは恐らく、資質上の限界点が見えて来ているという事だろう。真正の能力向上は努力感が苦にならない(充実感に満ちている)時に形成されるもののように思う。多くの日本人が中高生という生物学的には成長期にある時期に英語を学習しても実用レベルまで習得することができないのは、言語習得という資質に関しては10代半ばで既に減衰してしまっているという事だろう。
垂直方向での能力の向上は生物学的成長がほぼ完成する二十歳前後までに形成されたものがその人のベースで、それがその後の人生で上昇したとしてもごくわずかだと思う。成長後の大人に要求されるのは経験による成熟という水平方向的な広がり、イメージとしては三角形的なものから台形的になって行く感じだろうか。その者の持つベースに応じたレベルで、いろいろと経験し幅が広がって行き社会的能力が身に付いていく訳で、常識的に考えれば能力差は広がる事はあっても縮むことは無い。
坂東玉三郎が以前、師匠から受ける注意は一回だけ、その時その注意の意味を理解できなかったとき二度と注意はしてくれませんと、言っていたがそれが大人の指導というものだろう。厳しさというより合理的判断なのである。注意の内容の重要性を感じ取る資質が受け手に無い場合、いくら注意しても時間の無駄なのである。要するに資質がないのである。自分の資質に応じた範囲内でしか人は成長できい。それだけの事である。(逆も真で、自分の資質を超えて人を指導することは出来ない。指導される側の資質が勝っている場合、指導者にそれを受け入れる度量がないと、威圧という手段をとることになる。)
中年以降に能力向上の伸びしろなどないであろう。中高年を対象とした能力開発などと言ったものはフィクションであって、現実には能力の減衰が始まっている。もはや指導の対象者ではないのである。自然は冷徹である。中高年に必要なのは能力向上にむけた無駄な努力ではなく、どの様に自分自身を経年変化させていくかだと思う。自分を変えられるのは自分だけである。私が思うに中高年以降に大切なのは心を如何にしなやかにして行けるかだと思う。社会的成功を収めても晩年になって重度の心の硬化を発症し人間的にはまったく魅力のない高齢者もいれば、例え認知症になっても人間的に魅力的な高齢者も結構いるものである。
心をしなやかにしていくにはどうすればいいのか。「初々しさが大切なの 人に対しても世の中に対しても 人を人とも思わなくなったとき堕落が始まるのね」という茨木のり子の言葉が示唆に富んでいると思う。「自分を大切にするように、隣人を大切にせよ」「たとえ敵対する相手でも人として大事にしろ」というマルコの言葉を思い出す。人は人を人と思うレベルに応じて人格が陶冶され、人は人を人と思わなくなるレベルに応じて心が硬化し醜悪になって行く。
中高年になり若い時に比べ不機嫌になることが増えたり、他人を許容できなくなってきた場合には、自分の能力以上の事に手を出し過ぎていないかどうか、自分の生き方に何か問題がなかどうか、自分自身の退行から眼を逸らさず冷静に見つめ直す必要があると思う。人を人と思うゆとりを失わない為に。
ケアプランふくしあ 木藤
2021年02月24日
第二の人生を力強くスタート
こんにちは、1月からケアプランふくしあにお世話になっています、大原です。
リタイア後、介護保険者証も受け取り皆さんと近い介護支援専門員になりますが、若いスタッフに囲まれて楽しく仕事を再開しています。
コロナのワクチン接種がいよいよ始まっています。私も65歳以上の高齢者で対象になります。順番が回ってきたら受けたと思っています、皆さんはどうでしょうか?
接種後の不安も大きいと思いますが一人でも多くに方が接種できて、また前のような日常生活が戻ってくるならば・・・と強く思います。今外出も控えていたり、人との交流の機会が減っています、身体にもいろいろ影響が出てきています。前のように外出ができ、人との交流が取れて楽しく毎日が送れて、今年の桜をすっきりした気分で家族や友達、一人静かに眺めたいです。
花粉対策もしっかりしましょうね。 元気に過ごしてください。
ケアプランふくしあ 大原
リタイア後、介護保険者証も受け取り皆さんと近い介護支援専門員になりますが、若いスタッフに囲まれて楽しく仕事を再開しています。
コロナのワクチン接種がいよいよ始まっています。私も65歳以上の高齢者で対象になります。順番が回ってきたら受けたと思っています、皆さんはどうでしょうか?
接種後の不安も大きいと思いますが一人でも多くに方が接種できて、また前のような日常生活が戻ってくるならば・・・と強く思います。今外出も控えていたり、人との交流の機会が減っています、身体にもいろいろ影響が出てきています。前のように外出ができ、人との交流が取れて楽しく毎日が送れて、今年の桜をすっきりした気分で家族や友達、一人静かに眺めたいです。
花粉対策もしっかりしましょうね。 元気に過ごしてください。
ケアプランふくしあ 大原
2021年02月18日
雨水
寒暖差が大きい日が続いておりますが、皆さま体調変わる事なく過ごせておりますでしょうか?
さて、本日は雨水です。“雨水とは空から降るものが雪から雨に変わり、積もった雪や氷も解けて水になる“という意味だそうです。農耕の準備を始める目安とされ、春一番が吹く目安にもなっています。加えて雛人形をこの日に飾ると良縁に恵まれると言われているそうです。
なぜこの話題を書き出したかといいますと…先日訪問したご利用者様の家にとっても立派な雛人形が飾ってありました。その時はどうしてこの時期に?と思っていたのですが、このブログを書くにあたり調べていて合点がいきました。しっかり行事を知っている事、行っている事ってとても素敵な事ですね。
更に、別のお宅では数日前に蒔いた種から芽が出てきたと見せてくださりました。外出できなくても色々な物事を知っていて楽しまれている姿はとても尊敬します。
行事をしっかり知っていて行う事って簡単そうに聞こえますが、中々出来ない事と思います。ご利用者様の所にお邪魔して行事事に飾りをしたり行事食を召し上がっているのを見かけると時代や世代という理由で無くしてしまうのをとてももったいなく感じます。
…私自身も雨水を知らなかったので反省を込めて今回のブログと致します。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
さて、本日は雨水です。“雨水とは空から降るものが雪から雨に変わり、積もった雪や氷も解けて水になる“という意味だそうです。農耕の準備を始める目安とされ、春一番が吹く目安にもなっています。加えて雛人形をこの日に飾ると良縁に恵まれると言われているそうです。
なぜこの話題を書き出したかといいますと…先日訪問したご利用者様の家にとっても立派な雛人形が飾ってありました。その時はどうしてこの時期に?と思っていたのですが、このブログを書くにあたり調べていて合点がいきました。しっかり行事を知っている事、行っている事ってとても素敵な事ですね。
更に、別のお宅では数日前に蒔いた種から芽が出てきたと見せてくださりました。外出できなくても色々な物事を知っていて楽しまれている姿はとても尊敬します。
行事をしっかり知っていて行う事って簡単そうに聞こえますが、中々出来ない事と思います。ご利用者様の所にお邪魔して行事事に飾りをしたり行事食を召し上がっているのを見かけると時代や世代という理由で無くしてしまうのをとてももったいなく感じます。
…私自身も雨水を知らなかったので反省を込めて今回のブログと致します。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
2021年02月01日
新型コロナウイルス感染拡大による対応
1月に入ってから吉川市においても新型コロナウイルスの感染状況の様相が変わってきた印象があります。1月31日時点での吉川市の感染者累計216名、近隣の越谷市1,229名、三郷市584名、松伏町72名(1/28)となっています。私たちの日常の業務においても、陽性者の方と接する機会が出てきているような状況となっております。かような状況を受け、当事業所は職員の分散出勤という業務形態を取り入れリスクの分散と事業の継続を図っていくことと致しました。
新型コロナウイルスの潜伏期間は14日間であるとされており、平均では4〜6日ほどで発症するようです。検査の結果、新型コロナウイルス感染が陽性であった場合には、発症する3日前から発症後7~10日間程度が感染可能期間、いわゆる人にうつしてしまう可能性のある期間とされています。
潜伏期間が14日間あることから、新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した場合には、14日間の隔離が必要とされています。
今後、市内の感染状況に応じて、ご自宅への訪問は避け電話での相談や状況確認をさせて頂いたり、訪問が必要な時には、出来るだけ『1メートル以上の距離、15分以内』の滞在を心掛け私たち自身も感染拡大の媒介者にならないよう充分注意して参りたいと存じます。
皆様には担当ケアマネジャーと連絡が取りにくいといったようなご不便をおかけする事があろうかと思います。2グループに分かれて交代で出勤していますので、ご相談いただいた内容については担当ケアマネジャーに連絡・調整・対応させていただきます。何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
PCR検査の感度は北海道大学大学院医学研究院の豊嶋崇徳教授らの調査によると、約90%、特異度は99.9%以上だそうです。特異度が99.9%以上という事は、偽陽性の問題は殆どないのでしょうが、感度が約90%(検体採取時の手際や時期の影響がかなり大きいのであろうと思います)ということなので、数字上、新型コロナに感染していたとしてPCR検査を10回受けた時1回は陰性(偽陰性)の判定が出てしまうということなので、なかなか悩ましい数字だと思います。
感染症法上、新型コロナウイルス感染症については、期限付きで指定感染症2類相当として位置付けられていますが、その期間が令和3年2月6日をもって終了します。医療のひっ迫状況によっては、3類、4類相当として新たに位置付けられる事になるかも知れません。それによって医療、介護業界も影響を受ける事になると思われますので、注視して行きたいと思います。緊急事態宣言も2月7日までとなっておりますが、現状では延長になりそうです。
新型コロナウイルス感染症の拡大は続きそうです。立春近しとはいえまだまだ寒い日も続きそうです。くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。
ケアプランふくしあ 木藤
新型コロナウイルスの潜伏期間は14日間であるとされており、平均では4〜6日ほどで発症するようです。検査の結果、新型コロナウイルス感染が陽性であった場合には、発症する3日前から発症後7~10日間程度が感染可能期間、いわゆる人にうつしてしまう可能性のある期間とされています。
潜伏期間が14日間あることから、新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した場合には、14日間の隔離が必要とされています。
今後、市内の感染状況に応じて、ご自宅への訪問は避け電話での相談や状況確認をさせて頂いたり、訪問が必要な時には、出来るだけ『1メートル以上の距離、15分以内』の滞在を心掛け私たち自身も感染拡大の媒介者にならないよう充分注意して参りたいと存じます。
皆様には担当ケアマネジャーと連絡が取りにくいといったようなご不便をおかけする事があろうかと思います。2グループに分かれて交代で出勤していますので、ご相談いただいた内容については担当ケアマネジャーに連絡・調整・対応させていただきます。何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
PCR検査の感度は北海道大学大学院医学研究院の豊嶋崇徳教授らの調査によると、約90%、特異度は99.9%以上だそうです。特異度が99.9%以上という事は、偽陽性の問題は殆どないのでしょうが、感度が約90%(検体採取時の手際や時期の影響がかなり大きいのであろうと思います)ということなので、数字上、新型コロナに感染していたとしてPCR検査を10回受けた時1回は陰性(偽陰性)の判定が出てしまうということなので、なかなか悩ましい数字だと思います。
感染症法上、新型コロナウイルス感染症については、期限付きで指定感染症2類相当として位置付けられていますが、その期間が令和3年2月6日をもって終了します。医療のひっ迫状況によっては、3類、4類相当として新たに位置付けられる事になるかも知れません。それによって医療、介護業界も影響を受ける事になると思われますので、注視して行きたいと思います。緊急事態宣言も2月7日までとなっておりますが、現状では延長になりそうです。
新型コロナウイルス感染症の拡大は続きそうです。立春近しとはいえまだまだ寒い日も続きそうです。くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。
ケアプランふくしあ 木藤
2020年10月28日
インフルエンザ予防接種してきました
コロナ禍の中、プラスでインフルエンザ予防が必要な季節になってきました。
予防で大切なことの中に、マスクはもちろん、加湿、そして予防接種。その他にも歯科医院からの通信の中に舌のケアでインフルエンザの予防につながるとありましたので、ここに紹介します。
口の中は毎日覗くことができます。毎日覗くことで、何かの異常のサインに気が付くことができるかもしれません。
 舌苔(ぜったい)とは?
舌苔(ぜったい)とは?
細菌や食べかす、剝がれた粘膜などが舌の表面に付着してできた白い苔状のかたまりです。舌の表面に舌乳頭という細かい突起がたくさんありこの中に食べかすなどがたまり、細菌の住み家になります。
1日1回のペースで下の清掃を行うことで、口臭予防するだけでなく、インフルエンザや誤嚥性肺炎の予防に繋がります。
日中は唾液の分泌で細菌の増殖を抑えられますが寝ている間は唾液の分泌が減少し、自浄作用が弱くなるので、細菌のかたまりである舌苔の付着量は朝が1番多いと言われています。
 お手入れ方法
お手入れ方法
乾燥がある場合はまず指などで保湿剤を舌に塗り舌専用ブラシで喉の奥から手前に引きます。デリケートな部分なので力を入れすぎないようにすることが大切です。
暑い夏が終わり、秋になり、秋晴れのさわやかな1日は今までに何日もないような気がします。
秋晴れとは
雲ひとつない晴天の事。秋晴れをもたらすのは、秋の移動性高気圧で日本上空を乾燥した空気で覆うため空が一層澄んで見えます。また秋は夏と比べて日差しが弱まることも、すがすがしい心地にさせる理由の一つです。
さわやかな秋晴れの日を大切に、どう過ごすか考えたいと思います。
ケアプランふくしあ 檜木

予防で大切なことの中に、マスクはもちろん、加湿、そして予防接種。その他にも歯科医院からの通信の中に舌のケアでインフルエンザの予防につながるとありましたので、ここに紹介します。
口の中は毎日覗くことができます。毎日覗くことで、何かの異常のサインに気が付くことができるかもしれません。
 舌苔(ぜったい)とは?
舌苔(ぜったい)とは?細菌や食べかす、剝がれた粘膜などが舌の表面に付着してできた白い苔状のかたまりです。舌の表面に舌乳頭という細かい突起がたくさんありこの中に食べかすなどがたまり、細菌の住み家になります。

1日1回のペースで下の清掃を行うことで、口臭予防するだけでなく、インフルエンザや誤嚥性肺炎の予防に繋がります。
日中は唾液の分泌で細菌の増殖を抑えられますが寝ている間は唾液の分泌が減少し、自浄作用が弱くなるので、細菌のかたまりである舌苔の付着量は朝が1番多いと言われています。
 お手入れ方法
お手入れ方法乾燥がある場合はまず指などで保湿剤を舌に塗り舌専用ブラシで喉の奥から手前に引きます。デリケートな部分なので力を入れすぎないようにすることが大切です。

暑い夏が終わり、秋になり、秋晴れのさわやかな1日は今までに何日もないような気がします。
秋晴れとは

雲ひとつない晴天の事。秋晴れをもたらすのは、秋の移動性高気圧で日本上空を乾燥した空気で覆うため空が一層澄んで見えます。また秋は夏と比べて日差しが弱まることも、すがすがしい心地にさせる理由の一つです。
さわやかな秋晴れの日を大切に、どう過ごすか考えたいと思います。
ケアプランふくしあ 檜木
2020年10月14日
「閉じ込め症候群(locked-in syndrome)」
この仕事をしていると神経難病により徐々に動けなくなっていく方と関わる機会がある。その代表的な病気としてALSやパーキンソン病、多系統萎縮症(脊髄小脳変性症)などがある。これらの病気は真綿で首を締められるように段々とほぼ全身を動かす事が出来なくなり(閉じ込め症候群)、寝たきりとなって行く。
一方、脳幹の一部である橋と言われる部分(橋腹側部)が広範囲に障害(脳血管障害)されると、錐体路(神経の伝導路)と第5以下の脳神経の運動を司る伝導路が障害されるため垂直方向の眼球運動と瞬き以外の随意運動がすべて障害される。橋の背側にある感覚の経路と網様体は障害されない為、感覚は正常で、意識は清明である。救命されベッド上で意識が戻った時、ほぼ完璧な「閉じ込め症候群」になった自分を自覚する事になる。
このような回復の希望がない方の担当を依頼されたとき、正直、担当することを逡巡する時がある。
脊髄小脳変性症により25歳で夭逝された、木藤亜也の「1リットルの涙」からその経過を拾ってみる。
【16歳】
・たった3メートルの幅の廊下が渡れない。
【17歳】
・バ行、マ行の発音がしにくい。
《バ行もマ行も唇を閉じないと発音できない音なので、ストローで液体を吸うという動作もし辛くなっていたのかも知れない》
【18歳】
髪を切りました。だけどわたしは鏡を見ません。澄ましこんだ自分を見るのが嫌いなのです。また、いつも人に見せるような、あのニマーとした笑いや、ギュッと目をつむるとこなど、見られやしないからです。
《あのニマーとした笑いというのは、脳幹の障害からくる「強制笑い(意思や感情とは無関係)」のことだろう。》
頭の中に描く自分の姿は、健康だったころの普通の女の子しか浮かばない。姿見に写った自分は美しくなかった。背中が曲がって上半身が傾いている。
《病的な痩せ、筋緊張の亢進からくる関節の変形など病状の進行と共に容姿も変容して行く》
できなかったことが、厳しいリハビリでできるようになった、という事実が一つでも欲しい。
《慰めの言葉など何の役にも立たない魂の叫びに対して、支援者側は自分自身の無能性を前に、バカ面を下げて突っ立っている事しかできない。》
【19歳】
人の役に立ちたい→人に迷惑をかけないように自分のことだけでもやるようにしよう→人の世話にならんと生きていけない→人の重荷になって生きていく・・・・・・これが私の生い立ち!
お母さん、もう歩けない。ものにつかまっても、たつことができなくなりました。
死ねないから、しょうがないので息をして生きています。恐ろしい、言い方です。
《何かが出来る事、何かを成し遂げる事 (to do) によって、自分自身の存在理由が支えられていることは事実だろう。だが、それが出来なくなった時、人を支えてくれるのは、存在している事、生きている事 (to be) それだけで存在理由があるという視点で支えてくれる人間が周囲にいること、そういう人間関係が築けている事が必要なのだろう。人生の晩年に於いて人からの手助けが必要になった時の人間関係は、それまでの来し方の通信簿的側面があると同時に、人間関係は双方向性である以上、介護する側の家族もその人格的な度量が試される事になるのであろう。》
【20歳】
一日の大半を寝て過ごすようになってしまった。三度の食事も、飲み込みが悪く気道に入るのが怖くて少量しか食べられない。
ナ行、ダ行がはっきりしない。カ、サ、タ、ハ行も言い難い。いえる言葉がいくつ残っているだろう。
《導尿、胃ろう、気管切開になり、最終的に意思表示が出来なくなっていく》
一方ある日、突然、脳出血により「閉じ込め症候群」になった、43歳のフランス人、ジャン=ドミニック・ボービーという人が(20万回以上もの)瞬きをアルファベットに置き換えてもらうことで著した「潜水服は蝶の夢を見る」という書物がある。
「古ぼけたカーテンの向こうから、乳色に輝く朝がやってくる。踵が痛い、と僕は思う。頭も痛い。鉄の塊がのっているようだ。体じゅう、重たい潜水服を一式、着込んでしまったようなのだ。」
「頭のてっぺんからつま先まで、全身が麻痺。けれど、意識や知能はまったく元のままだ。自分という人間の内側に閉じ込められてしまったようなものだった。そうして、ただ一ヵ所、かろうじて動かせる左の目で、瞬きをすることだけが、ことばの代わりに残された唯一の方法となった。」
「例えばある日、僕は自分を、笑ってしまいそうになる。44歳にもなって、赤ん坊のように、体を洗われ、うつ伏せにされ、拭かれ、服にくるまれるとは。まるで退行現象だなと、おかしくてたまらない。ところがあくる日は、おなじことが、全て悲壮の極みとして迫ってくる。そうして、介護士が頬いっぱいに塗ってくれたシェービングクリームの中に、涙が流れ落ちて行く。」
尊大で横柄な医師のお決まりの質問「二重に見えますか?」に対して、ボービーは心の中で、『はい、バカが二人見えます。』と切り返す。
《過酷な現実の中で、ただ、暗闇の中に落下して行かないためには、シニカルさも必要なのだろう。崖から転落しないようしがみつく際に爪を立てるように。》
不治の病など神経難病に限らずのっぴきのならない現実を背負い、その現実と真摯に向き合い自分自身が置かれている状況を、必死に明(諦)らめて生きて行こうとしている人と、仕事上関わることになる私はその人の内面世界にどのように映し出されるのだろうか。必死さに比例したその人が放つ透過力のある光源によってあたかもX線に照射され体内を裸にされてしまうのと同じように、自分自身の内面性がすべてあらわにされてしまうような怖さを感じる時がある。
ケアプランふくしあ 木藤
一方、脳幹の一部である橋と言われる部分(橋腹側部)が広範囲に障害(脳血管障害)されると、錐体路(神経の伝導路)と第5以下の脳神経の運動を司る伝導路が障害されるため垂直方向の眼球運動と瞬き以外の随意運動がすべて障害される。橋の背側にある感覚の経路と網様体は障害されない為、感覚は正常で、意識は清明である。救命されベッド上で意識が戻った時、ほぼ完璧な「閉じ込め症候群」になった自分を自覚する事になる。
このような回復の希望がない方の担当を依頼されたとき、正直、担当することを逡巡する時がある。
脊髄小脳変性症により25歳で夭逝された、木藤亜也の「1リットルの涙」からその経過を拾ってみる。
【16歳】
・たった3メートルの幅の廊下が渡れない。
【17歳】
・バ行、マ行の発音がしにくい。
《バ行もマ行も唇を閉じないと発音できない音なので、ストローで液体を吸うという動作もし辛くなっていたのかも知れない》
【18歳】
髪を切りました。だけどわたしは鏡を見ません。澄ましこんだ自分を見るのが嫌いなのです。また、いつも人に見せるような、あのニマーとした笑いや、ギュッと目をつむるとこなど、見られやしないからです。
《あのニマーとした笑いというのは、脳幹の障害からくる「強制笑い(意思や感情とは無関係)」のことだろう。》
頭の中に描く自分の姿は、健康だったころの普通の女の子しか浮かばない。姿見に写った自分は美しくなかった。背中が曲がって上半身が傾いている。
《病的な痩せ、筋緊張の亢進からくる関節の変形など病状の進行と共に容姿も変容して行く》
できなかったことが、厳しいリハビリでできるようになった、という事実が一つでも欲しい。
《慰めの言葉など何の役にも立たない魂の叫びに対して、支援者側は自分自身の無能性を前に、バカ面を下げて突っ立っている事しかできない。》
【19歳】
人の役に立ちたい→人に迷惑をかけないように自分のことだけでもやるようにしよう→人の世話にならんと生きていけない→人の重荷になって生きていく・・・・・・これが私の生い立ち!
お母さん、もう歩けない。ものにつかまっても、たつことができなくなりました。
死ねないから、しょうがないので息をして生きています。恐ろしい、言い方です。
《何かが出来る事、何かを成し遂げる事 (to do) によって、自分自身の存在理由が支えられていることは事実だろう。だが、それが出来なくなった時、人を支えてくれるのは、存在している事、生きている事 (to be) それだけで存在理由があるという視点で支えてくれる人間が周囲にいること、そういう人間関係が築けている事が必要なのだろう。人生の晩年に於いて人からの手助けが必要になった時の人間関係は、それまでの来し方の通信簿的側面があると同時に、人間関係は双方向性である以上、介護する側の家族もその人格的な度量が試される事になるのであろう。》
【20歳】
一日の大半を寝て過ごすようになってしまった。三度の食事も、飲み込みが悪く気道に入るのが怖くて少量しか食べられない。
ナ行、ダ行がはっきりしない。カ、サ、タ、ハ行も言い難い。いえる言葉がいくつ残っているだろう。
《導尿、胃ろう、気管切開になり、最終的に意思表示が出来なくなっていく》
一方ある日、突然、脳出血により「閉じ込め症候群」になった、43歳のフランス人、ジャン=ドミニック・ボービーという人が(20万回以上もの)瞬きをアルファベットに置き換えてもらうことで著した「潜水服は蝶の夢を見る」という書物がある。
「古ぼけたカーテンの向こうから、乳色に輝く朝がやってくる。踵が痛い、と僕は思う。頭も痛い。鉄の塊がのっているようだ。体じゅう、重たい潜水服を一式、着込んでしまったようなのだ。」
「頭のてっぺんからつま先まで、全身が麻痺。けれど、意識や知能はまったく元のままだ。自分という人間の内側に閉じ込められてしまったようなものだった。そうして、ただ一ヵ所、かろうじて動かせる左の目で、瞬きをすることだけが、ことばの代わりに残された唯一の方法となった。」
「例えばある日、僕は自分を、笑ってしまいそうになる。44歳にもなって、赤ん坊のように、体を洗われ、うつ伏せにされ、拭かれ、服にくるまれるとは。まるで退行現象だなと、おかしくてたまらない。ところがあくる日は、おなじことが、全て悲壮の極みとして迫ってくる。そうして、介護士が頬いっぱいに塗ってくれたシェービングクリームの中に、涙が流れ落ちて行く。」
尊大で横柄な医師のお決まりの質問「二重に見えますか?」に対して、ボービーは心の中で、『はい、バカが二人見えます。』と切り返す。
《過酷な現実の中で、ただ、暗闇の中に落下して行かないためには、シニカルさも必要なのだろう。崖から転落しないようしがみつく際に爪を立てるように。》
不治の病など神経難病に限らずのっぴきのならない現実を背負い、その現実と真摯に向き合い自分自身が置かれている状況を、必死に明(諦)らめて生きて行こうとしている人と、仕事上関わることになる私はその人の内面世界にどのように映し出されるのだろうか。必死さに比例したその人が放つ透過力のある光源によってあたかもX線に照射され体内を裸にされてしまうのと同じように、自分自身の内面性がすべてあらわにされてしまうような怖さを感じる時がある。
ケアプランふくしあ 木藤
2020年10月07日
|| |̩|||| || ||̩| | |̩|||
暑さが終わり、肌寒く感じる日が多くなってまいりましたが、皆様体調変わる事なく過ごせておりますでしょうか?
さて、本日は“バーコードの日“だそうです。普段身近にあって気にした事もなかったバーコード。いい機会だったので少しバーコードについて調べてみました。
そもそもバーコードは1952年の今日にアメリカで特許を得た所から始まったそうです。しかし、バーコードが実用化されるのはもっと先でした。約20年の時を経て、1973年にアメリカでバーコードが制定され、日本が追う形で1978年に制定されました。しかし、メーカー側の負担が大きく普及には至らなかったそうです。日本で普及したのは1984年にセブンイレブンが本格的に導入し、全ての納入業者にバーコードを使用することを求めたそうです。これをきっかけに商品にバーコードがついていくことになり、現在に至るそうです。大企業の影響力で一気に普及したわけですね。(だいぶ大まかに書いておりますが…)
歴史に関しては、このくらいにしておいてバーコードが普及したことにより、生活がどのように変わったかを考えてみました。
まず最初に思ったのはバーコードが無い時のレジ打ちです。商品についている金額を見て、手打ちする。金額がついていない店では商品の値段を覚える。それらをレジが混雑しないように素早く行う。中々大変そうですね。レジ打ち新人の負担がものすごい気がします。商品管理も大変です。そして消費税が導入されます。消費税導入時にバーコードがなかったら…恐ろしい。
子供の頃に通っていた駄菓子屋さんの店主は全ての商品の値段を暗記してその場で暗算して金銭のやりとりをしていた事を思い出しました。そして消費税取られてなかったんだなぁ…
バーコードがあることによって消費側だけでなくアルバイトや字が読めない外国人等、働く側の人たちにも、ものすごいメリットがあるわけですね。普段身近にあるものでもそれぞれに歴史があって、どんどん進化していってどんどん便利になっていっているんですね。
今では国勢調査の紙にもバーコード(QRコード)がついています。サイトへのアクセスや連絡先交換にも使われています。今では当たり前ですが、学生の頃は相手のメールアドレスを聞いて手打ちしていました。1文字間違えていて送れなかった事も多々ありました。その後、赤外線通信やQRコードに変わっていきました。次はどんなシステムに変わりますかね?
長くなってきましたのでこの辺で。最後まで読んでいただいてありがとうございました。
- - -
今月はケアプランふくしあが担当しています。
さて、本日は“バーコードの日“だそうです。普段身近にあって気にした事もなかったバーコード。いい機会だったので少しバーコードについて調べてみました。
そもそもバーコードは1952年の今日にアメリカで特許を得た所から始まったそうです。しかし、バーコードが実用化されるのはもっと先でした。約20年の時を経て、1973年にアメリカでバーコードが制定され、日本が追う形で1978年に制定されました。しかし、メーカー側の負担が大きく普及には至らなかったそうです。日本で普及したのは1984年にセブンイレブンが本格的に導入し、全ての納入業者にバーコードを使用することを求めたそうです。これをきっかけに商品にバーコードがついていくことになり、現在に至るそうです。大企業の影響力で一気に普及したわけですね。(だいぶ大まかに書いておりますが…)
歴史に関しては、このくらいにしておいてバーコードが普及したことにより、生活がどのように変わったかを考えてみました。
まず最初に思ったのはバーコードが無い時のレジ打ちです。商品についている金額を見て、手打ちする。金額がついていない店では商品の値段を覚える。それらをレジが混雑しないように素早く行う。中々大変そうですね。レジ打ち新人の負担がものすごい気がします。商品管理も大変です。そして消費税が導入されます。消費税導入時にバーコードがなかったら…恐ろしい。
子供の頃に通っていた駄菓子屋さんの店主は全ての商品の値段を暗記してその場で暗算して金銭のやりとりをしていた事を思い出しました。そして消費税取られてなかったんだなぁ…
バーコードがあることによって消費側だけでなくアルバイトや字が読めない外国人等、働く側の人たちにも、ものすごいメリットがあるわけですね。普段身近にあるものでもそれぞれに歴史があって、どんどん進化していってどんどん便利になっていっているんですね。
今では国勢調査の紙にもバーコード(QRコード)がついています。サイトへのアクセスや連絡先交換にも使われています。今では当たり前ですが、学生の頃は相手のメールアドレスを聞いて手打ちしていました。1文字間違えていて送れなかった事も多々ありました。その後、赤外線通信やQRコードに変わっていきました。次はどんなシステムに変わりますかね?
長くなってきましたのでこの辺で。最後まで読んでいただいてありがとうございました。
- - -
今月はケアプランふくしあが担当しています。
2020年06月17日
いい話
はじめまして。4月からケアプランふくしあでお世話になっております金子と申します。以後よろしくお願い致します。コロナによる自粛も少しずつ解除され外に出る機会が増えたり、車通りもだいぶ増えてきました。
マスクをしながらの外出は暑く かなりこたえますが皆様は体調変わることなくお過ごしでしょうか?
かなりこたえますが皆様は体調変わることなくお過ごしでしょうか?
さて、ここ最近での深イイ話をご紹介させていただきます。
担当ご利用者様宅に訪問に行った時の話。身の回りのこともゆっくり行いながらおひとりで暮らしている方です。訪問時は必ず門を開けておいてくれているのですがいつもは午後1番でお邪魔させていただいています。その日は受診だったため夕方お邪魔させていただいていたところドアをノックして入ってくる女性の方。「大丈夫?こんな時間に門が開いているし」と話しながら入ってこられました。
ご近所の方が門が開いていることを心配して様子をみに来てくださったのです。しかも以前担当させていた方の奥様でした。久しぶりにお会いしたことやご近所の方を心配して声掛けをしてくださっていることにすごくうれしく思いました
まだまだご近所力があることにとても感銘を受けました。この地域で介護支援をさせていただく中でご近所の方の見守り、声掛けは本当にありがたいものです
 今後もこういった支援の輪が広がることを願いつつ私自身もその輪の中にしっかり入っていけるようにご支援してまいります。
今後もこういった支援の輪が広がることを願いつつ私自身もその輪の中にしっかり入っていけるようにご支援してまいります。
マスクをしながらの外出は暑く
 かなりこたえますが皆様は体調変わることなくお過ごしでしょうか?
かなりこたえますが皆様は体調変わることなくお過ごしでしょうか?さて、ここ最近での深イイ話をご紹介させていただきます。
担当ご利用者様宅に訪問に行った時の話。身の回りのこともゆっくり行いながらおひとりで暮らしている方です。訪問時は必ず門を開けておいてくれているのですがいつもは午後1番でお邪魔させていただいています。その日は受診だったため夕方お邪魔させていただいていたところドアをノックして入ってくる女性の方。「大丈夫?こんな時間に門が開いているし」と話しながら入ってこられました。
ご近所の方が門が開いていることを心配して様子をみに来てくださったのです。しかも以前担当させていた方の奥様でした。久しぶりにお会いしたことやご近所の方を心配して声掛けをしてくださっていることにすごくうれしく思いました

まだまだご近所力があることにとても感銘を受けました。この地域で介護支援をさせていただく中でご近所の方の見守り、声掛けは本当にありがたいものです

 今後もこういった支援の輪が広がることを願いつつ私自身もその輪の中にしっかり入っていけるようにご支援してまいります。
今後もこういった支援の輪が広がることを願いつつ私自身もその輪の中にしっかり入っていけるようにご支援してまいります。