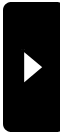› 介護の「ふくしあ」-スタッフブログ › ケアプランふくしあ-居宅介護支援
2018年03月14日
冬から春へ
最近は暖かいj日が続き、桜の開花も早まりそうですね。
ケアプランふくしあの事務所は、桜通りと銀杏通りの間にあります。
ケアマネージャーの仕事は、訪問することも日々ありますが、車や場所により、自転車で移動します。
春の桜通り、秋の銀杏通りは特に自転車での移動時はつい、立ち止まり見上げてしまいます。圧巻ですよね
桜通りの桜の木 542本ソメイヨシノが3㎞にわたり並んでいるそうですよ!
吉川市も『桜まつり』なるものを企画して夜はライトアップなんかもするみたいです。
待ち遠しいですね
さて・・・
日中は暖かいですがまだまだ朝晩冷え込むことがあるのがこの季節。気温の差も大きかったりしますね。
花粉症の私としましては毎日花粉とも戦っているわけですが、 今年はきつい!特に目がかゆくて
今年はきつい!特に目がかゆくて
今回は健康豆知識として知りえたことを少し紹介します
(腸を温めることで、免疫力あっぷ!!)
1、高タンパク低カロリーの食品を積極的に摂取する。
体を温めるにはタンパク質が必要 鳥のささ身、マグロの赤身、豆腐他
2、土の中で育った野菜や冬が旬の野菜で冷えない体を作る。
体を温めてくれる野菜 ゴボウ、人参(土の中で) ネギ、イモ類(冬が旬)これらの野菜には血行をよくするビタミンEや血管の機能をよくするビタミンCが含まれている。
(日光を浴びよう!!)
1、日光には紫外線が含まれていますが、多量に浴びなければ健康な方はプラスに!
紫外線の刺激により体内でビタミンDが育成される。
ビタミンD(骨粗しょう症予防、他うつ病予防、癌や歯周病、自己免疫疾患にかかるのを防ぐ)
ただし、日光にあたる頻度は、週に3回程度、1回あたり15分程度がいいとされているそうですよ。
これからの季節 お花見をしながらお散歩もいいですね
今回はこの辺で ケアプランふくしあ 檜木でした
ケアプランふくしあの事務所は、桜通りと銀杏通りの間にあります。
ケアマネージャーの仕事は、訪問することも日々ありますが、車や場所により、自転車で移動します。
春の桜通り、秋の銀杏通りは特に自転車での移動時はつい、立ち止まり見上げてしまいます。圧巻ですよね

桜通りの桜の木 542本ソメイヨシノが3㎞にわたり並んでいるそうですよ!
吉川市も『桜まつり』なるものを企画して夜はライトアップなんかもするみたいです。
待ち遠しいですね

さて・・・
日中は暖かいですがまだまだ朝晩冷え込むことがあるのがこの季節。気温の差も大きかったりしますね。
花粉症の私としましては毎日花粉とも戦っているわけですが、
 今年はきつい!特に目がかゆくて
今年はきつい!特に目がかゆくて
今回は健康豆知識として知りえたことを少し紹介します
(腸を温めることで、免疫力あっぷ!!)
1、高タンパク低カロリーの食品を積極的に摂取する。
体を温めるにはタンパク質が必要 鳥のささ身、マグロの赤身、豆腐他
2、土の中で育った野菜や冬が旬の野菜で冷えない体を作る。
体を温めてくれる野菜 ゴボウ、人参(土の中で) ネギ、イモ類(冬が旬)これらの野菜には血行をよくするビタミンEや血管の機能をよくするビタミンCが含まれている。
(日光を浴びよう!!)
1、日光には紫外線が含まれていますが、多量に浴びなければ健康な方はプラスに!
紫外線の刺激により体内でビタミンDが育成される。
ビタミンD(骨粗しょう症予防、他うつ病予防、癌や歯周病、自己免疫疾患にかかるのを防ぐ)
ただし、日光にあたる頻度は、週に3回程度、1回あたり15分程度がいいとされているそうですよ。
これからの季節 お花見をしながらお散歩もいいですね

今回はこの辺で ケアプランふくしあ 檜木でした
2018年03月07日
幸せになる方法(ロバート・ウォールディンガー編)
ハーバード大学には80年間続いている「 成人発達研究 」という有名な調査があります。
一生を通して、私たちを健康で幸福にしてくれるのはなんだろう? そう問われて、思い浮かぶ答えはなんだろうか。ハーバード大学の心理学者ロバート・ウォールディンガー教授らによる成人発達研究によると、8割の人は「富を蓄えること」と答え、そのうち5割の目標はさらに「有名になること」としたという。
1930年代に始まったこの研究では、75年間724人の男性を追跡記録していった。史上最長期間をかけて成人の生活を追った調査で、教授はその4代目の研究主任だ。この調査では、ふたつの環境下から研究の対象者を選んでいる。ひとつ目のくくりはハーバード大学の2年生で、ふたつ目のグループはボストンの極貧環境で水道すらままならない環境で育った少年達だった。彼らを長期にわたって定期的に訪問してはインタビューを行ない、医療記録までを調査対象としていった。
被験者の人生を追いかけていくと、工場労働者もいれば、弁護士になったもの、レンガ職人や医師、アルコール中毒者や統合失調症患者もいれば、ひとりはアメリカの大統領になったものもいたという。
こうして追跡した何万ページもの情報を見ると、浮き上がってくることがあった。それは人を健康で幸福にするものは、富でも名声でも、いい仕事を得て働くことでもなく……、“よい人間関係を築くこと”に尽きるというのだ。そして、人間関係に関して大きな教訓がみられたという。
ひとつは、家族でも友達でもコミュニティでも、周りとつながりが上手な人は健康で長生きをするというもの。逆に孤独は命取りで、孤立化を受け入れている人は、あまり幸せを感じず、脳機能の減退も早期に始まるという結果だった。
たとえば結婚をして伴侶と一緒にいても、ケンカが多ければストレスはたまるし、健康には悪影響となる。さらに、人といても孤独を感じることになるだろう。愛情があるいい人間関係を築くことが、人を守ってくれるというわけだ。
以上、インターネットから。
自己中の塊のような国民性と思えるアメリカ人の幸福度を左右する重要因子が良い人間関係だったとは意外な事なのか、将又、アメリカという国は日本人が思う以上にファンダメンタリズムな国家であって、社会の共通基盤としてキリスト教があり、その下で個々人が結びつく(インテグレート)ことに高い価値を感じているのか?
今、日本での親子関係は、子供と同居するより、お金で介護サービスを買った方が楽だと考えている人は少なくないと思います。お金を使えば、面倒な人間関係を省けます。人間関係にお金を介在させればさせるほど、面倒な人間関係を省けると同時に人間関係は希薄になります。とどのつまりが、無縁社会となる。3.11後、「絆」の復権が叫ばれましたが、面倒な人間関係を覚悟しなければ、「絆」は創れません。日本社会を実質的に下支えしていた共通基盤としての家を単位とした共同体はもはや無い。個人を単位として共同体(コニュニティー)を形成する文化的基盤もない。根無し草のような戦後民主主義があるだけである。その中で高齢者福祉を福祉政策から利用者が主体的に選べるサービスという旗印のもと保険制度に変更しました。その変遷後に行政がやっている事は、サービス利用に対するアクセス制限強化、低所得者へのしわ寄せ、介護労働の官製ダンピングという方向性での制度改正を行い続けているというのが実態だと思います。要は財政難からお金で問題を解決することが出来なくなっているということです。無縁社会は、戦後の日本人が日本特有の同調圧力の高い面倒な「絆」からの解放を求めてきた成果物です。その成果物を成り立たせていたお金が無くなった時から新しい「絆」の再生に向けて私達は佇むことになるのでしょうか。因みに、「世界幸福度ランキング2017」によると、日本は主観的幸福度51位、G7の最下位、OECD加盟35カ国の27番目だそうです。
ケアプランふくしあ 木藤
一生を通して、私たちを健康で幸福にしてくれるのはなんだろう? そう問われて、思い浮かぶ答えはなんだろうか。ハーバード大学の心理学者ロバート・ウォールディンガー教授らによる成人発達研究によると、8割の人は「富を蓄えること」と答え、そのうち5割の目標はさらに「有名になること」としたという。
1930年代に始まったこの研究では、75年間724人の男性を追跡記録していった。史上最長期間をかけて成人の生活を追った調査で、教授はその4代目の研究主任だ。この調査では、ふたつの環境下から研究の対象者を選んでいる。ひとつ目のくくりはハーバード大学の2年生で、ふたつ目のグループはボストンの極貧環境で水道すらままならない環境で育った少年達だった。彼らを長期にわたって定期的に訪問してはインタビューを行ない、医療記録までを調査対象としていった。
被験者の人生を追いかけていくと、工場労働者もいれば、弁護士になったもの、レンガ職人や医師、アルコール中毒者や統合失調症患者もいれば、ひとりはアメリカの大統領になったものもいたという。
こうして追跡した何万ページもの情報を見ると、浮き上がってくることがあった。それは人を健康で幸福にするものは、富でも名声でも、いい仕事を得て働くことでもなく……、“よい人間関係を築くこと”に尽きるというのだ。そして、人間関係に関して大きな教訓がみられたという。
ひとつは、家族でも友達でもコミュニティでも、周りとつながりが上手な人は健康で長生きをするというもの。逆に孤独は命取りで、孤立化を受け入れている人は、あまり幸せを感じず、脳機能の減退も早期に始まるという結果だった。
たとえば結婚をして伴侶と一緒にいても、ケンカが多ければストレスはたまるし、健康には悪影響となる。さらに、人といても孤独を感じることになるだろう。愛情があるいい人間関係を築くことが、人を守ってくれるというわけだ。
以上、インターネットから。
自己中の塊のような国民性と思えるアメリカ人の幸福度を左右する重要因子が良い人間関係だったとは意外な事なのか、将又、アメリカという国は日本人が思う以上にファンダメンタリズムな国家であって、社会の共通基盤としてキリスト教があり、その下で個々人が結びつく(インテグレート)ことに高い価値を感じているのか?
今、日本での親子関係は、子供と同居するより、お金で介護サービスを買った方が楽だと考えている人は少なくないと思います。お金を使えば、面倒な人間関係を省けます。人間関係にお金を介在させればさせるほど、面倒な人間関係を省けると同時に人間関係は希薄になります。とどのつまりが、無縁社会となる。3.11後、「絆」の復権が叫ばれましたが、面倒な人間関係を覚悟しなければ、「絆」は創れません。日本社会を実質的に下支えしていた共通基盤としての家を単位とした共同体はもはや無い。個人を単位として共同体(コニュニティー)を形成する文化的基盤もない。根無し草のような戦後民主主義があるだけである。その中で高齢者福祉を福祉政策から利用者が主体的に選べるサービスという旗印のもと保険制度に変更しました。その変遷後に行政がやっている事は、サービス利用に対するアクセス制限強化、低所得者へのしわ寄せ、介護労働の官製ダンピングという方向性での制度改正を行い続けているというのが実態だと思います。要は財政難からお金で問題を解決することが出来なくなっているということです。無縁社会は、戦後の日本人が日本特有の同調圧力の高い面倒な「絆」からの解放を求めてきた成果物です。その成果物を成り立たせていたお金が無くなった時から新しい「絆」の再生に向けて私達は佇むことになるのでしょうか。因みに、「世界幸福度ランキング2017」によると、日本は主観的幸福度51位、G7の最下位、OECD加盟35カ国の27番目だそうです。
ケアプランふくしあ 木藤
2017年10月25日
人の話を聞くことの難しさ
『いくら親しい人との楽しいおしゃべりでも、一方的に聞き手にならなければならないときは疲れるのです。職場でも、家庭でも、このようなことはけっこうあるもので、上の者が下の者の話を聞くのがいいのですが、実際には逆のことのほうが多いのです。上司と飲んだときは、家に帰ってからそれを吐き、あらためて家で飲み直さないと眠れないという人がいましたが、これは上司の、酒ではなくて話が飲みこめなかったからです。飲みこめない話をたくさん聞かされると、本当に下痢をする人もいます。話を自分なりに消化できなかったからです。
母親から、祖母や父親のぐちを聞かされつづけた子どもには、心理的な症状が出ることが知られていますが、このように心理的症状を出す人の多くは、家族の葛藤の調整役をしています。調整役とは家族の話の聞き手です。消化できない話や納得できない話をじっと聞かされると、聞いた人が苦しむのです。
プロのカウンセラーにしても、自分の身内の話を聞くのは、ある意味でいちばんやっかいです。相手が相談者だと話を聞くのは一時間の枠内ですが、身内となると時間は無制限だからです。』
『プロのカウンセラーの聞く技術』東山紘久著
東山紘久氏が、人の話を聞いている途中で、「しかし」、「けれど」とか「でも」という、逆説の接続詞や接続助詞が出てきたら、それはプロの聞き手としは失格だと言っています。しかもそれは、逆説の接続詞を実際に口にしたら失格だというようなレベルではなく、聞き手として、相手に対して「しかし」とか「でも」といったような反発モード的な心の状態になった瞬間に失格だという意味です。プロカウンセラーの凄味のようなものを感じさせられます。ベテランになればなるほど、カウンセラーはListenするだけで、殆どAskする事はないそうです。それが出来るためには、相手がこの人(カウンセラー)だったら、心の悩みを相談することが出来るという気持ちになれるような、自分から語り出すことが出来るようなプレゼンスとしてカウンセラーが機能しなければならない訳で並大抵な事でないと思います。
人の話を聞くという姿勢の対極的場面としてテレビの政治討論があると思います。相手を論破する為に初めから反発モードで、討論というよりは互いに自己主張しているだけの不毛な状況です。
「子曰く、君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」。政治とは正に、小人の衆といった観があります。君子というのは一つの理想像であって、現実の政治に於いて君子でいられる人間はいないというのが人間の性のような気がします。
『村(高森草庵)で、インドの若者とアメリカの若者が共同生活を始めました。ある日、アメリカの若者が訴えに来ました。
「インド人とは、とても一緒に暮らせない」
「何故?」
「だって、あいつらはどこにでも小便をするんだもの!」
翌日、インドの若者が訴えに来ました。
「アメリカ人とは、とても共同生活は出来ない」
「どうして?」
「だって、あいつらは小便をしたあと、決して手を洗わないんだ!」
両方とも自分が正しいということについて、少しも疑っていません。相手の立場に共感しようなどという余裕は、微塵もあらばこそ。両者の訴えでは、インド人の方がもう少し深刻でしょう。アメリカ人の訴えは衛生上の不潔感に基づいていますが、インド人の場合には宗教的不潔感が関連しているからです。
この山の共同生活でも、正しい食生活についての論争が続きました。
生物化学を専攻していたアメリカ人青年が、塩の使い方が多すぎる、といって批判しました。一方、料理を勉強してきた日本人女性達は一歩も譲りません。塩だけではなく、アメリカ人は玄米とごまを要求します。他の人々は米は五分づき。彼女達は手間が倍近くなるのを引受けて、彼に玄米やごまを用意すますが、時々遅くなります。最も正統派たるべき食事が二の次にされるのが、彼には不満のようです。それやこれやで、互いの感情が円満でなくなったとき、私は一つの実話を話しました。
日本青年協力隊々員の一人が、インドで農業指導をしました。こうすれば生産は倍になる、ということで手とり足とり教えました。いいえ、教えたつもりでした。ところが、一向に実行してくれない。その気配もない。それで彼はもう一度、教えようとしました。すると、向こうの人達はもう我慢できない。というわけで、彼の手足を縛って川の中へ放りこみました。彼の怒りようといったら大変なもの。
「ひでえやつらだ。ひとがせっかく親切に教えてやろうというのに!」
インドの農民は言いました。
「全く、ひでえやつだ。俺達には俺達の伝来のやり方があり、受けついだ知恵があるのに自分のところのやり方を押しつけようとしやがって。黙っておとなしく聞いていれば、いい気になりやがる。いい気のなるにも程があらぁ!」
この話をした反応が、また面白かった。アメリカの青年はうれしげに、私に尋ねました。
「あとでその日本人はどうなりましたか。自分の非を悟ったでしょうか」
彼女達は言いました。
「彼は結局、わからなかったみたいね。おかしいわね」
自分のための話でもあったとは、夢にも思いつきません。
人間は皆、地表に穴を掘りあけない特別なもぐら、です。気付かぬうちに自分が絶対だ、と思うのです。』
『藍の水』押田茂人神父著
人間は他の動物と違って言葉というシンボルを多彩に操り、他者との交流を行っているが、逆にその事で上滑りのような状況を作り出してしまい、哀しいほど人の話を聞く事の出来ない生き物なのかも知れない。夫婦、親子や兄弟といった間に於いてすら「和して同ぜず」といった関係性を築けている人が果たしてどれ位いるのであろうか。むしろ、どんな人間関係よりもよりハードルが高いような気もする。お互いの自律性のレベルによって、その家族の「和して同ぜず」~「同じて和せず(共依存)」といった関係性の偏差値が決まってくるのであろう。
人の話をしっかりと聞くことができるためには、相手に対する深い思い遣りと自他の区別を確りと保つことのできる自律性の確立が要請されているのだと思います。対人援助職という立場にいる身としては、君子などという途方もない地平はさて置いて、せめてもぐらの住人として定住してしまわないよう、とぼとぼと歩んでいきたいと思います。
母親から、祖母や父親のぐちを聞かされつづけた子どもには、心理的な症状が出ることが知られていますが、このように心理的症状を出す人の多くは、家族の葛藤の調整役をしています。調整役とは家族の話の聞き手です。消化できない話や納得できない話をじっと聞かされると、聞いた人が苦しむのです。
プロのカウンセラーにしても、自分の身内の話を聞くのは、ある意味でいちばんやっかいです。相手が相談者だと話を聞くのは一時間の枠内ですが、身内となると時間は無制限だからです。』
『プロのカウンセラーの聞く技術』東山紘久著
東山紘久氏が、人の話を聞いている途中で、「しかし」、「けれど」とか「でも」という、逆説の接続詞や接続助詞が出てきたら、それはプロの聞き手としは失格だと言っています。しかもそれは、逆説の接続詞を実際に口にしたら失格だというようなレベルではなく、聞き手として、相手に対して「しかし」とか「でも」といったような反発モード的な心の状態になった瞬間に失格だという意味です。プロカウンセラーの凄味のようなものを感じさせられます。ベテランになればなるほど、カウンセラーはListenするだけで、殆どAskする事はないそうです。それが出来るためには、相手がこの人(カウンセラー)だったら、心の悩みを相談することが出来るという気持ちになれるような、自分から語り出すことが出来るようなプレゼンスとしてカウンセラーが機能しなければならない訳で並大抵な事でないと思います。
人の話を聞くという姿勢の対極的場面としてテレビの政治討論があると思います。相手を論破する為に初めから反発モードで、討論というよりは互いに自己主張しているだけの不毛な状況です。
「子曰く、君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」。政治とは正に、小人の衆といった観があります。君子というのは一つの理想像であって、現実の政治に於いて君子でいられる人間はいないというのが人間の性のような気がします。
『村(高森草庵)で、インドの若者とアメリカの若者が共同生活を始めました。ある日、アメリカの若者が訴えに来ました。
「インド人とは、とても一緒に暮らせない」
「何故?」
「だって、あいつらはどこにでも小便をするんだもの!」
翌日、インドの若者が訴えに来ました。
「アメリカ人とは、とても共同生活は出来ない」
「どうして?」
「だって、あいつらは小便をしたあと、決して手を洗わないんだ!」
両方とも自分が正しいということについて、少しも疑っていません。相手の立場に共感しようなどという余裕は、微塵もあらばこそ。両者の訴えでは、インド人の方がもう少し深刻でしょう。アメリカ人の訴えは衛生上の不潔感に基づいていますが、インド人の場合には宗教的不潔感が関連しているからです。
この山の共同生活でも、正しい食生活についての論争が続きました。
生物化学を専攻していたアメリカ人青年が、塩の使い方が多すぎる、といって批判しました。一方、料理を勉強してきた日本人女性達は一歩も譲りません。塩だけではなく、アメリカ人は玄米とごまを要求します。他の人々は米は五分づき。彼女達は手間が倍近くなるのを引受けて、彼に玄米やごまを用意すますが、時々遅くなります。最も正統派たるべき食事が二の次にされるのが、彼には不満のようです。それやこれやで、互いの感情が円満でなくなったとき、私は一つの実話を話しました。
日本青年協力隊々員の一人が、インドで農業指導をしました。こうすれば生産は倍になる、ということで手とり足とり教えました。いいえ、教えたつもりでした。ところが、一向に実行してくれない。その気配もない。それで彼はもう一度、教えようとしました。すると、向こうの人達はもう我慢できない。というわけで、彼の手足を縛って川の中へ放りこみました。彼の怒りようといったら大変なもの。
「ひでえやつらだ。ひとがせっかく親切に教えてやろうというのに!」
インドの農民は言いました。
「全く、ひでえやつだ。俺達には俺達の伝来のやり方があり、受けついだ知恵があるのに自分のところのやり方を押しつけようとしやがって。黙っておとなしく聞いていれば、いい気になりやがる。いい気のなるにも程があらぁ!」
この話をした反応が、また面白かった。アメリカの青年はうれしげに、私に尋ねました。
「あとでその日本人はどうなりましたか。自分の非を悟ったでしょうか」
彼女達は言いました。
「彼は結局、わからなかったみたいね。おかしいわね」
自分のための話でもあったとは、夢にも思いつきません。
人間は皆、地表に穴を掘りあけない特別なもぐら、です。気付かぬうちに自分が絶対だ、と思うのです。』
『藍の水』押田茂人神父著
人間は他の動物と違って言葉というシンボルを多彩に操り、他者との交流を行っているが、逆にその事で上滑りのような状況を作り出してしまい、哀しいほど人の話を聞く事の出来ない生き物なのかも知れない。夫婦、親子や兄弟といった間に於いてすら「和して同ぜず」といった関係性を築けている人が果たしてどれ位いるのであろうか。むしろ、どんな人間関係よりもよりハードルが高いような気もする。お互いの自律性のレベルによって、その家族の「和して同ぜず」~「同じて和せず(共依存)」といった関係性の偏差値が決まってくるのであろう。
人の話をしっかりと聞くことができるためには、相手に対する深い思い遣りと自他の区別を確りと保つことのできる自律性の確立が要請されているのだと思います。対人援助職という立場にいる身としては、君子などという途方もない地平はさて置いて、せめてもぐらの住人として定住してしまわないよう、とぼとぼと歩んでいきたいと思います。
2017年10月18日
秋を感じるもの
こんにちは
10月も後半戦に突入しました。今年もあと2か月半
今は毎日1日の重みや大切さを感じながら仕事に駆けずり回っています!
ところで、皆様の周りに、秋 は見えますか?
風景であったり、食べ物であったり、服装であったり…虫の声?


暑い夏から解放され、ようやく過ごしやすい季節になったと思っていたら、この数日の寒さ!!
通勤が自転車の私としては朝に晩に骨身にしみます。
巷ではすでにインフルエンザの流行の話が入ってきています。外から帰ったら手洗いうがいは忘れずに
この短い秋、1日を大切に過ごしましょう。天気の良い日は散歩をしながら秋を探してみてください。
こんな秋が見つかりましたとコメントをいただけたら嬉しいです。
ではまた来週に…ケアプランふくしあ 檜木でした。

10月も後半戦に突入しました。今年もあと2か月半

今は毎日1日の重みや大切さを感じながら仕事に駆けずり回っています!
ところで、皆様の周りに、秋 は見えますか?
風景であったり、食べ物であったり、服装であったり…虫の声?


暑い夏から解放され、ようやく過ごしやすい季節になったと思っていたら、この数日の寒さ!!
通勤が自転車の私としては朝に晩に骨身にしみます。
巷ではすでにインフルエンザの流行の話が入ってきています。外から帰ったら手洗いうがいは忘れずに
この短い秋、1日を大切に過ごしましょう。天気の良い日は散歩をしながら秋を探してみてください。
こんな秋が見つかりましたとコメントをいただけたら嬉しいです。
ではまた来週に…ケアプランふくしあ 檜木でした。
2017年10月11日
老いを感じる時
高齢者の気持ちを察することは、他の年代とは違って特有の難しさがあるように思われます。高齢期以外の年代はその時期を当事者として体験した後に、その時期を振り返って客観的に見つめ直すことが出来ますが、高齢期だけは主観的に体験した後に客観的に見つめ直すという視点がありません。
国立長寿医療研究センターで下方浩史氏らが行っている高齢者を対象とした縦断研究において、「老いの自覚」をどんなときに感じるかという調査結果を『「老ける人」「老けない人」はここが違う』という著書で次ように報告されています。
『私達の行っている縦断研究において、「老いの自覚」をどんなときに感じるかを聞いてみたところ、「身体的な変化」よりも「人間関係の変化」を挙げた人のほうが多かったのです。「縦断研究」では、「老いの自覚」について、心理面の面接調査のなかで次のような質問をしています。
「最近6ヶ月の間で、老いを自覚したことはありますか?」
これに「はい」と答えた人には、
「老いを自覚した最大の理由はなんですか?」と質問します。
理由については、病気/身体・容姿の変化/体力の低下/人間関係の変化/心理的兆候(記憶力が悪くなった、など)/その他、などの選択肢があり、その中から選んでもらうようにしました。
すると、いちばん回答数が多かったのが、「人間関係の変化」だった、という訳です。具体例でいうと、一つは職場を引退したり、家族や友人の死に直面したり、といった、人との別れにつながる人間関係の変化を挙げた人が多くいました。離別とういのはいかにも寂しく、老いを考えるきっかけになっても不思議ではありません。
その一方で、孫の誕生や、長寿を祝うための家族の集まりといった、一見喜ばしいようなことも、老いを自覚させる出来事になり得るようなのです。還暦や古希、喜寿といった長寿の祝いも、「ご苦労様、これからはゆっくり休んでください」という意味が込められています。こうした出来事は、周囲が自分を老人と見ていることははっきりと自覚させられる瞬間です。自分の意識に関らず、周りから「あなたはもう高齢ですよ」というレッテルを貼られてしまうようなものです。
このように周りから押しつけられる形で老いを自覚させられると、自ら自覚するよりも大きなショックを受けるのでしょう。(鏡や写真に写った自分の姿にふと驚き自覚的ショックを受けることもあると思うが。)
なかでもいちばんこたえるのが、「わが子と立場が逆転してしまうとき」のようです。今までずっと立場が下だったはずの子どもから、ある日急に「もう歳なんだから」といたわられたり、慰められたり、馬鹿にされたり、といった体験です。確かにいかにも腹立たしく、情けない体験に違いありません。ショックが強いだけに、老いを自覚する瞬間として印象に残りやすいのだと思います。』
この親子の立場が逆転する時期をどう乗り越えていくのかは、各々家族に与えられた課題なのでしょう。家族と同居している事で逆に孤立感が深まる場面があることは想像に難くないと思います。高齢者の自殺者の多くは家族と同居しており、単身生活は全体の5%以下です。
評論家の堀秀彦は、「老人が社会にもとめているが、けっして口に出せないものは『いたわり』であるという。老人とは闘い終わった人間であり、いたわり、哀れみ、尊敬といった複雑なものをまぜた目を痛切にもとめている」と語っている。
「受ける手がどんなに美しい形のものか」というゲーテのコトバは、助けを求める人と援助する側の人との授受が自然になされている状況を描写したものであろうが、この様な援助を求める手の差し出し方が出来るためには、相当、自我臭が脱落(とつらく)した人でなければ出来ないような気がします。だから『いたわり』を求めることはけっして口には出せないのでしょう。
アベノミクスによる一億総活躍しなければならない今の社会が高齢者に求めているのは介護を必要としない「自立」です。しかし、「老い」というものがあたかも予防できるような、ひたすら健康増進に努めなければならないような、老年期というものをそんな狭いひたすら管理されねばならない一点に収斂させてしまっていいのだろうかと、私は思う。ただ言えることは、自立という価値を最優先させる社会環境の中では、誰にとっても老年期は生き難いと思うのだが。
ケアプランふくしあ 木藤
国立長寿医療研究センターで下方浩史氏らが行っている高齢者を対象とした縦断研究において、「老いの自覚」をどんなときに感じるかという調査結果を『「老ける人」「老けない人」はここが違う』という著書で次ように報告されています。
『私達の行っている縦断研究において、「老いの自覚」をどんなときに感じるかを聞いてみたところ、「身体的な変化」よりも「人間関係の変化」を挙げた人のほうが多かったのです。「縦断研究」では、「老いの自覚」について、心理面の面接調査のなかで次のような質問をしています。
「最近6ヶ月の間で、老いを自覚したことはありますか?」
これに「はい」と答えた人には、
「老いを自覚した最大の理由はなんですか?」と質問します。
理由については、病気/身体・容姿の変化/体力の低下/人間関係の変化/心理的兆候(記憶力が悪くなった、など)/その他、などの選択肢があり、その中から選んでもらうようにしました。
すると、いちばん回答数が多かったのが、「人間関係の変化」だった、という訳です。具体例でいうと、一つは職場を引退したり、家族や友人の死に直面したり、といった、人との別れにつながる人間関係の変化を挙げた人が多くいました。離別とういのはいかにも寂しく、老いを考えるきっかけになっても不思議ではありません。
その一方で、孫の誕生や、長寿を祝うための家族の集まりといった、一見喜ばしいようなことも、老いを自覚させる出来事になり得るようなのです。還暦や古希、喜寿といった長寿の祝いも、「ご苦労様、これからはゆっくり休んでください」という意味が込められています。こうした出来事は、周囲が自分を老人と見ていることははっきりと自覚させられる瞬間です。自分の意識に関らず、周りから「あなたはもう高齢ですよ」というレッテルを貼られてしまうようなものです。
このように周りから押しつけられる形で老いを自覚させられると、自ら自覚するよりも大きなショックを受けるのでしょう。(鏡や写真に写った自分の姿にふと驚き自覚的ショックを受けることもあると思うが。)
なかでもいちばんこたえるのが、「わが子と立場が逆転してしまうとき」のようです。今までずっと立場が下だったはずの子どもから、ある日急に「もう歳なんだから」といたわられたり、慰められたり、馬鹿にされたり、といった体験です。確かにいかにも腹立たしく、情けない体験に違いありません。ショックが強いだけに、老いを自覚する瞬間として印象に残りやすいのだと思います。』
この親子の立場が逆転する時期をどう乗り越えていくのかは、各々家族に与えられた課題なのでしょう。家族と同居している事で逆に孤立感が深まる場面があることは想像に難くないと思います。高齢者の自殺者の多くは家族と同居しており、単身生活は全体の5%以下です。
評論家の堀秀彦は、「老人が社会にもとめているが、けっして口に出せないものは『いたわり』であるという。老人とは闘い終わった人間であり、いたわり、哀れみ、尊敬といった複雑なものをまぜた目を痛切にもとめている」と語っている。
「受ける手がどんなに美しい形のものか」というゲーテのコトバは、助けを求める人と援助する側の人との授受が自然になされている状況を描写したものであろうが、この様な援助を求める手の差し出し方が出来るためには、相当、自我臭が脱落(とつらく)した人でなければ出来ないような気がします。だから『いたわり』を求めることはけっして口には出せないのでしょう。
アベノミクスによる一億総活躍しなければならない今の社会が高齢者に求めているのは介護を必要としない「自立」です。しかし、「老い」というものがあたかも予防できるような、ひたすら健康増進に努めなければならないような、老年期というものをそんな狭いひたすら管理されねばならない一点に収斂させてしまっていいのだろうかと、私は思う。ただ言えることは、自立という価値を最優先させる社会環境の中では、誰にとっても老年期は生き難いと思うのだが。
ケアプランふくしあ 木藤
2017年05月26日
クロノスとカイロス
人生80年生きるとすると、人に与えられた一生の日数は29,200日(除閏年)、時間は700,800時間(約4,200万分、約25億秒)です。ちょっとタバコを一服5分、それを1日10回、それは健康を害する上に1日3000秒(40年喫煙した場合4,380万秒;約1年4ヶ月)の無駄遣いです。ちょっと立ち話のつもりがあっという間の2時間、なんと7200秒の無駄使い。そんなことはもう止めて、その3000秒、7200秒は「時間貯蓄銀行」に預けましょう。ミヒャエル・エンデの「モモ」である。この作品は、時は金なりのメタファーでもある。
民俗学の世界から介護の世界に入られた六車由実という方が民俗学で培った聞き書き調査を応用した「驚きの介護民俗学」という本を出版されています。その著書の中に次のような事が記されていました。『同僚の介護士から、「話を聞くことが介護なの?・・・(略)・・・そんな事していたら仕事がまわらないじゃない。・・・(略)・・・」そんな事を言うのは介護士として失格だと思った。その人の生き方を知ることこそ介護の基本じゃないか、と思っていたからだ。けれど、現場の業務に追われるなかで、結局自分も同じになっている。一方で、自分自身の介護技術の向上に伴って、技術的な達成感の喜びは強く感じるようになっていった。しかし、そこで感じる介護の喜びは、これまでの利用者との関係のなかで感じられるものとは明らかに異なる。極端に言えば、利用者と接しているのに、そこには利用者の存在が希薄となっている。ただ自分の技術に酔っているだけなのだ。驚きのままに聞き書きを進めていたときに、目の前に利用者の背負ってきた歴史が立体的に浮かび上がってきて、利用者の人としての存在がとてつもなく大きく感じられたのが嘘のようだった。』
人が集まって何かを制度化し組織的活動をするときには、そこは、客観的に計れる時間、定量化された時間、クロノスが支配している。一方、各個人にとっての時間には一回限りの質を伴う歴史的時間、定量化できない時間、カイロスがある。ケアとは本来、カイロスに於ける出会いである。いわゆる一期一会である。しかし制度化された中での介護業務は時間管理を要求する。従って例えどんなに良い制度であったとしても、クロノスとカイロスの矛盾は生じてしまう。そこに本当に現場の突端にいる介護士、特に心ある介護士であればある程、その矛盾に苦しむ。その葛藤を少しでも軽減する為には、制度に遊びを許すゆとりが必要なのである。しかし、経済的合理性に最大の価値を置いている現代社会ではカイロス的時間は無駄として評価されない。
フッサールが指摘していることだが、16世紀にガリレオ・ガリレイが振り子の原理を応用した振り子時計によって、かつては地球の自転や公転などに基づく自然とつながった生活実感を伴う天文学的な定義だった時間を測定する技術を手にいれた。そしてそれ以降、人間はひたすら自然の数学化を推し進めて来た。現在の1秒の長さの定義は、セシウム原子の固有の振動数9,192,631,770回を1秒としています。このセシウム原子時計でも、3,000万年に1秒の誤差を生じるそうです。現在、さらに光格子時計という新たな基準が構想されているそうです。この時計は140億年で誤差が100秒しか生じないそうです。
近代以前の社会では、昼と夜、ケとハレなど状況によって時間は均質ではなくもっと多義的なものだった。今は日常の生活感覚とまったく結びつかない均質で抽象的時間が逆に私たちの日常生活を支配しているような状況が作られてしまっている。今、証券取引では、コンピューターが1,000分の1秒単位で為替、資源情報、政治情勢などを判断して、「適切な銘柄、株数、価格」を発注するという。アメリカの証券会社では少しでも情報伝達速度を上げるためにネットワークを結ぶケーブルを出来るだけ直線になるようインフラを整備している所もあるそうです。超一瞬でも早くいい銘柄を見つけて動くことが利益を上げる上で今の証券取引にとって重要な戦略になっているそうです。
何か、私には狂気の沙汰のような気がしています。時間の測定技術を研ぎ澄ました先にどんな社会がもたらされてくるのでしょうか。超抽象的時間に生を適応させて生きて行かなければならない社会が疎外しているのは、子供と老人です。時間管理がシビアな日本で少子化が止まらない、老齢人口が増えて困った困ったの大合唱が起こっている、この事は疎外している証左だと思っています。逆に言えば、このクロノス的世界観に収まりきらない代表的な人達は子供と老人という事です。ならば日本だけでなく全世界的に老齢人口が増えて、今の社会システムからはみ出す人達がどんどん増加して行くことは一つの希望であり、このクロノス的社会を打破してくれるかもしれない光明なのではなかと密な期待感をもって私は仕事をしています。
いでよ、モモ太郎じいさんず・モモ子ばあさんず!
ケアプランふくしあ 木藤
民俗学の世界から介護の世界に入られた六車由実という方が民俗学で培った聞き書き調査を応用した「驚きの介護民俗学」という本を出版されています。その著書の中に次のような事が記されていました。『同僚の介護士から、「話を聞くことが介護なの?・・・(略)・・・そんな事していたら仕事がまわらないじゃない。・・・(略)・・・」そんな事を言うのは介護士として失格だと思った。その人の生き方を知ることこそ介護の基本じゃないか、と思っていたからだ。けれど、現場の業務に追われるなかで、結局自分も同じになっている。一方で、自分自身の介護技術の向上に伴って、技術的な達成感の喜びは強く感じるようになっていった。しかし、そこで感じる介護の喜びは、これまでの利用者との関係のなかで感じられるものとは明らかに異なる。極端に言えば、利用者と接しているのに、そこには利用者の存在が希薄となっている。ただ自分の技術に酔っているだけなのだ。驚きのままに聞き書きを進めていたときに、目の前に利用者の背負ってきた歴史が立体的に浮かび上がってきて、利用者の人としての存在がとてつもなく大きく感じられたのが嘘のようだった。』
人が集まって何かを制度化し組織的活動をするときには、そこは、客観的に計れる時間、定量化された時間、クロノスが支配している。一方、各個人にとっての時間には一回限りの質を伴う歴史的時間、定量化できない時間、カイロスがある。ケアとは本来、カイロスに於ける出会いである。いわゆる一期一会である。しかし制度化された中での介護業務は時間管理を要求する。従って例えどんなに良い制度であったとしても、クロノスとカイロスの矛盾は生じてしまう。そこに本当に現場の突端にいる介護士、特に心ある介護士であればある程、その矛盾に苦しむ。その葛藤を少しでも軽減する為には、制度に遊びを許すゆとりが必要なのである。しかし、経済的合理性に最大の価値を置いている現代社会ではカイロス的時間は無駄として評価されない。
フッサールが指摘していることだが、16世紀にガリレオ・ガリレイが振り子の原理を応用した振り子時計によって、かつては地球の自転や公転などに基づく自然とつながった生活実感を伴う天文学的な定義だった時間を測定する技術を手にいれた。そしてそれ以降、人間はひたすら自然の数学化を推し進めて来た。現在の1秒の長さの定義は、セシウム原子の固有の振動数9,192,631,770回を1秒としています。このセシウム原子時計でも、3,000万年に1秒の誤差を生じるそうです。現在、さらに光格子時計という新たな基準が構想されているそうです。この時計は140億年で誤差が100秒しか生じないそうです。
近代以前の社会では、昼と夜、ケとハレなど状況によって時間は均質ではなくもっと多義的なものだった。今は日常の生活感覚とまったく結びつかない均質で抽象的時間が逆に私たちの日常生活を支配しているような状況が作られてしまっている。今、証券取引では、コンピューターが1,000分の1秒単位で為替、資源情報、政治情勢などを判断して、「適切な銘柄、株数、価格」を発注するという。アメリカの証券会社では少しでも情報伝達速度を上げるためにネットワークを結ぶケーブルを出来るだけ直線になるようインフラを整備している所もあるそうです。超一瞬でも早くいい銘柄を見つけて動くことが利益を上げる上で今の証券取引にとって重要な戦略になっているそうです。
何か、私には狂気の沙汰のような気がしています。時間の測定技術を研ぎ澄ました先にどんな社会がもたらされてくるのでしょうか。超抽象的時間に生を適応させて生きて行かなければならない社会が疎外しているのは、子供と老人です。時間管理がシビアな日本で少子化が止まらない、老齢人口が増えて困った困ったの大合唱が起こっている、この事は疎外している証左だと思っています。逆に言えば、このクロノス的世界観に収まりきらない代表的な人達は子供と老人という事です。ならば日本だけでなく全世界的に老齢人口が増えて、今の社会システムからはみ出す人達がどんどん増加して行くことは一つの希望であり、このクロノス的社会を打破してくれるかもしれない光明なのではなかと密な期待感をもって私は仕事をしています。
いでよ、モモ太郎じいさんず・モモ子ばあさんず!
ケアプランふくしあ 木藤
2017年05月18日
爽やかな5月
事務所の窓から 桜の木が見えるのですが緑が鮮やかで本当に気持ちいいです
木々の緑とつつじのピンク色…PCを打ちながら窓の外を見て少しの休憩も!
今年は長く桜を楽しむことができましたが、今は季節が春から初夏へ・・・
ただ日によって、まだ朝晩は寒い日もありますので、皆様体調管理だけはお気を付けて。
洋服で調整する、汗をかいたら拭く、水分を取る等々
さて、今日は第3木曜日。デイサービス『ふくしあの家』でオレンジカフェが開かれていました!!

エレクトーンの音色と、素敵な歌声がとても心地よく
私自身もとても癒されました
吉川市では、いろいろな場所でオレンジカフェやサロンなど開催し、様々な方との
情報交換や相談の場として利用できるようになってきました。すばらしいことです。
もっともっと気楽に足が運べて、小さなことでも相談しやすい場!!になりますように
話しは変わりますが
ケアプランふくしあも今はケアマネージャーが3人います。
日々利用者様と向き合う中で一緒に悩み、相談をしながらすすめています。
こちらでも、いつでもご相談してください。まずはお電話お待ちしています。
ケアプランふくしあ 檜木
木々の緑とつつじのピンク色…PCを打ちながら窓の外を見て少しの休憩も!
今年は長く桜を楽しむことができましたが、今は季節が春から初夏へ・・・
ただ日によって、まだ朝晩は寒い日もありますので、皆様体調管理だけはお気を付けて。
洋服で調整する、汗をかいたら拭く、水分を取る等々
さて、今日は第3木曜日。デイサービス『ふくしあの家』でオレンジカフェが開かれていました!!

エレクトーンの音色と、素敵な歌声がとても心地よく
私自身もとても癒されました

吉川市では、いろいろな場所でオレンジカフェやサロンなど開催し、様々な方との
情報交換や相談の場として利用できるようになってきました。すばらしいことです。
もっともっと気楽に足が運べて、小さなことでも相談しやすい場!!になりますように

話しは変わりますが
ケアプランふくしあも今はケアマネージャーが3人います。
日々利用者様と向き合う中で一緒に悩み、相談をしながらすすめています。
こちらでも、いつでもご相談してください。まずはお電話お待ちしています。
ケアプランふくしあ 檜木
2017年05月11日
0と1
『ほんとうの供養』
世の中には、働きたいと思っても働けない人がいる。身体や精神の障害があるために、なかなか働けないのである。私がお会いする方たちのなかにはそんな人がおられる。病院に入院しているが、病院内での軽作業くらいならできる、という程度の方が、次のようなことを言われた。
自分は最近、母を亡くしたが、自分は今は何の収入もないので、母のために何かするということはできない。しかし、院内の作業で、入院中の老人たちのためにおむつをたたんで整理する仕事をしているとき、そのおむつのひとつひとつを扱うのが、母への供養と思ってやっている、というのである。
この話を聞いて、この方の母を思う気持ちの深さに心を打たれたが、それに加えて思ったことは、その病院内で、おそらく「寝たきり」などと言われている老人の方々が、この人の母への供養に貢献しておられる、ということである。何もせず寝ていて、おむつをかえてもらっているだけと思う人もあろう。 しかし、私には、そのような老人の一人一人のたましいが、母を失った人の心を慰め、その供養に日夜参加している、というイメージがみえてくるのである。
毎日働けることはありがたいことだ。それによって、われわれはお金や物や多くのものを得ている。しかし、誰かの供養のためにほんとうに参加するなどということをしているだろうか。
河合隼雄 平成3年読売新聞夕刊コラムより
『抱く』
生まれたばかりの道人を 両腕に抱いて正座する
道人という 人間の名前をつけられてはいるけれども
腕の内にあるものは
深く静けく 深くやさしい ひとつの振動である
神の現前である
人の名で呼ぶには いかにも惜しい
人の声で呼ぶには いかにも惜しい
生まれたばかりの赤ちゃんを 両腕に抱いて正座する
山尾 三省 詩集「びろう葉帽子の下で」より
「命がやっていることは『伸びて縮んで』それだけである。」これはスリランカの僧侶アルボムッレ・スマナサーラのコトバである。卓見だと思う。人生複雑に思うけれど原理はいたって単純である。「伸びて縮んで」「0と1」「offとon」の多重構造である。私たちは外界や体内からの色々な刺激(X)を求心路を介して入力し、それを脳で情報処理し信号(Y)として遠心路を介して効果器(筋肉)に出力している。この「0と1」の信号が骨格筋に伝達されなくなったものがALSである。まさに骨格筋の伸び縮みが出来なくなったそれだけの事である。しかし、それがどれほど大変なことか。
人間この世に産まれて来て生きる為にまず産声を上げる。自発呼吸である。「0と1」の現前である。だが、私たちは剥き出しの命のままでは生きていけない。成長と共に社会の中で生きていく上でいろいろなペルソナを身につけ社会的活動を行っていく。やがて老い社会の一線から退き私たちはいろいろなペルソナを失(剥奪・解放)い、最後は衰弱し下顎呼吸を呈し剥き出しの命となり、やがて「伸びて縮んで」が出来なくなりこの世を去っていく。
人間どんなに威張ってみたところでも、あるいはどんなに卑下してみたところでも、やっていることは、「伸びて縮んで、伸びて縮んで」「0と1、offとon」それだけである。
鼓動・呼吸・蠕動・脳波などといった命の振動が奏でる基層低音を深く観取することが出来たならば、人は命の絶対的平等性という地平を闢くことができるのであろうか。ただ、現代という時代はこの命の振動が奏でる幽き基層低音に耳を澄ますにはあまりにも人工物に囲まれ自然から遊離してしまっている社会だと思う。命の振動への眼差しを醸成し難い社会に於いて、少子化が進行するのはパラレルな関係にあるように思えてならない。
ケアプランふくしあ 木藤
世の中には、働きたいと思っても働けない人がいる。身体や精神の障害があるために、なかなか働けないのである。私がお会いする方たちのなかにはそんな人がおられる。病院に入院しているが、病院内での軽作業くらいならできる、という程度の方が、次のようなことを言われた。
自分は最近、母を亡くしたが、自分は今は何の収入もないので、母のために何かするということはできない。しかし、院内の作業で、入院中の老人たちのためにおむつをたたんで整理する仕事をしているとき、そのおむつのひとつひとつを扱うのが、母への供養と思ってやっている、というのである。
この話を聞いて、この方の母を思う気持ちの深さに心を打たれたが、それに加えて思ったことは、その病院内で、おそらく「寝たきり」などと言われている老人の方々が、この人の母への供養に貢献しておられる、ということである。何もせず寝ていて、おむつをかえてもらっているだけと思う人もあろう。 しかし、私には、そのような老人の一人一人のたましいが、母を失った人の心を慰め、その供養に日夜参加している、というイメージがみえてくるのである。
毎日働けることはありがたいことだ。それによって、われわれはお金や物や多くのものを得ている。しかし、誰かの供養のためにほんとうに参加するなどということをしているだろうか。
河合隼雄 平成3年読売新聞夕刊コラムより
『抱く』
生まれたばかりの道人を 両腕に抱いて正座する
道人という 人間の名前をつけられてはいるけれども
腕の内にあるものは
深く静けく 深くやさしい ひとつの振動である
神の現前である
人の名で呼ぶには いかにも惜しい
人の声で呼ぶには いかにも惜しい
生まれたばかりの赤ちゃんを 両腕に抱いて正座する
山尾 三省 詩集「びろう葉帽子の下で」より
「命がやっていることは『伸びて縮んで』それだけである。」これはスリランカの僧侶アルボムッレ・スマナサーラのコトバである。卓見だと思う。人生複雑に思うけれど原理はいたって単純である。「伸びて縮んで」「0と1」「offとon」の多重構造である。私たちは外界や体内からの色々な刺激(X)を求心路を介して入力し、それを脳で情報処理し信号(Y)として遠心路を介して効果器(筋肉)に出力している。この「0と1」の信号が骨格筋に伝達されなくなったものがALSである。まさに骨格筋の伸び縮みが出来なくなったそれだけの事である。しかし、それがどれほど大変なことか。
人間この世に産まれて来て生きる為にまず産声を上げる。自発呼吸である。「0と1」の現前である。だが、私たちは剥き出しの命のままでは生きていけない。成長と共に社会の中で生きていく上でいろいろなペルソナを身につけ社会的活動を行っていく。やがて老い社会の一線から退き私たちはいろいろなペルソナを失(剥奪・解放)い、最後は衰弱し下顎呼吸を呈し剥き出しの命となり、やがて「伸びて縮んで」が出来なくなりこの世を去っていく。
人間どんなに威張ってみたところでも、あるいはどんなに卑下してみたところでも、やっていることは、「伸びて縮んで、伸びて縮んで」「0と1、offとon」それだけである。
鼓動・呼吸・蠕動・脳波などといった命の振動が奏でる基層低音を深く観取することが出来たならば、人は命の絶対的平等性という地平を闢くことができるのであろうか。ただ、現代という時代はこの命の振動が奏でる幽き基層低音に耳を澄ますにはあまりにも人工物に囲まれ自然から遊離してしまっている社会だと思う。命の振動への眼差しを醸成し難い社会に於いて、少子化が進行するのはパラレルな関係にあるように思えてならない。
ケアプランふくしあ 木藤
2017年05月04日
正さという病
毎月、皆様のご自宅を訪問させて頂き面談など行う私たちケアマネジャーの仕事は、対人援助職などと言われ、基本的に介護上何らかの課題(問題)を抱えている方を対象として活動しています。
この仕事をしていれば、誰でも多かれ少なかれいわゆる困難事例(虐待・困窮・独居・認知症の老々介護等)と呼ばれるようなケースに遭遇します。色々な問題が次から次へと発生し、かつ、それに対して有効な対応が取れず、不全感だけが募ってくることがあります。
精神科医の春日武彦医師は、援助者側が不全感を強く抱く時、それは援助者側が描いている「こうあるべきだという生活状況」にクライアント(利用者)を持って行こうとするコントロール願望が根底にありそれが強すぎるのではないかと指摘されています。言い換えれば権力欲かも知れません。
厄介なことにこのコントロール願望は善意との親和性が高く、対人援助場面では混然一体となって作用している。善意の裏には「私は正しいことをしている」という妙なスケベ根性みたいなものと他人に認めてもらいたいという「承認欲求」が影のように張り付いている。善意が相手と噛み合っている内はいいが、いったんボタンの掛け違いのような状態に陥ると、援助者側は「私はあなたの為にこんなに頑張っているのに」、一方相手方は「余計なことをしていい迷惑だ」という状況が醸成されてしまう。最悪、憎悪だけが残る事になってしまう。場が影に支配されてしまったようなものである。この構図は親子関係にも当てはまる。親が子供に対して。あるいは子供が介護が必要になった親に対して。逃げ場のない家族介護が時に地獄と化す所以である。コントロール願望や善意といったものに付きまとう影は自覚し難く、人間関係に於いて非常に根深い問題であり、この問題から完全にフリーでいられる人間はいない。
そもそも介護というものは、基本的には誰にでも訪れる自然現象としての老衰から今まで一人で出来ていた事が出来なくなり、誰かの援助が必要になったという事です。従って介護というものは、もともと解決すべき問題として向き合うべきものではなく、当人とその家族が取り組み続けなければならない人生上の課題として向き合うべきものと思っています。
ケアマネジャーが出来ることは、当事者の方々が課題に向き合えるように支援する事だけで、問題を解決したり、取り除いたりするなどといった事は出来ません。そもそも人生上の問題はその人ものである以上、赤の他人がどうこうすることなど出来るはずもありません。善意という心根は人として非常に貴重なものであるが、一人の人間が善意で居続けることなど出来はしない。従って職業として、年単位で関係性を持つことになるであろう方に対して対人援助という活動を行っていく立場にある者としては、何とかしてあげたいなどという安易な善意で相手と向き合うことは決して誉められるような事ではなく、むしろ慎まなければいけない振る舞いなのだと思います。
自分が担当しているケースというものは、ある意味自分自身を映し出す鏡のようなものでもある。不全感だけを強く感じていたり、或いは、妙な達成感を抱いている時、自分自身がコントロール願望や善意に伴う影に振り回されていないかどうか、対人援助職としては、常に内省する必要があると思う。善意の根底にある「私は正しいことをしている」という(潜在的)意識は、時に不健全な対人関係を形成させてしまう危険性に対する援助者側の感性を麻痺させてしまう。この対人援助に伴う病理に対する病識を欠いたえげつないケアマネジャーだけにはならないよう努力して行きたいと思っています。
ケアプランふくしあ 木藤
この仕事をしていれば、誰でも多かれ少なかれいわゆる困難事例(虐待・困窮・独居・認知症の老々介護等)と呼ばれるようなケースに遭遇します。色々な問題が次から次へと発生し、かつ、それに対して有効な対応が取れず、不全感だけが募ってくることがあります。
精神科医の春日武彦医師は、援助者側が不全感を強く抱く時、それは援助者側が描いている「こうあるべきだという生活状況」にクライアント(利用者)を持って行こうとするコントロール願望が根底にありそれが強すぎるのではないかと指摘されています。言い換えれば権力欲かも知れません。
厄介なことにこのコントロール願望は善意との親和性が高く、対人援助場面では混然一体となって作用している。善意の裏には「私は正しいことをしている」という妙なスケベ根性みたいなものと他人に認めてもらいたいという「承認欲求」が影のように張り付いている。善意が相手と噛み合っている内はいいが、いったんボタンの掛け違いのような状態に陥ると、援助者側は「私はあなたの為にこんなに頑張っているのに」、一方相手方は「余計なことをしていい迷惑だ」という状況が醸成されてしまう。最悪、憎悪だけが残る事になってしまう。場が影に支配されてしまったようなものである。この構図は親子関係にも当てはまる。親が子供に対して。あるいは子供が介護が必要になった親に対して。逃げ場のない家族介護が時に地獄と化す所以である。コントロール願望や善意といったものに付きまとう影は自覚し難く、人間関係に於いて非常に根深い問題であり、この問題から完全にフリーでいられる人間はいない。
そもそも介護というものは、基本的には誰にでも訪れる自然現象としての老衰から今まで一人で出来ていた事が出来なくなり、誰かの援助が必要になったという事です。従って介護というものは、もともと解決すべき問題として向き合うべきものではなく、当人とその家族が取り組み続けなければならない人生上の課題として向き合うべきものと思っています。
ケアマネジャーが出来ることは、当事者の方々が課題に向き合えるように支援する事だけで、問題を解決したり、取り除いたりするなどといった事は出来ません。そもそも人生上の問題はその人ものである以上、赤の他人がどうこうすることなど出来るはずもありません。善意という心根は人として非常に貴重なものであるが、一人の人間が善意で居続けることなど出来はしない。従って職業として、年単位で関係性を持つことになるであろう方に対して対人援助という活動を行っていく立場にある者としては、何とかしてあげたいなどという安易な善意で相手と向き合うことは決して誉められるような事ではなく、むしろ慎まなければいけない振る舞いなのだと思います。
自分が担当しているケースというものは、ある意味自分自身を映し出す鏡のようなものでもある。不全感だけを強く感じていたり、或いは、妙な達成感を抱いている時、自分自身がコントロール願望や善意に伴う影に振り回されていないかどうか、対人援助職としては、常に内省する必要があると思う。善意の根底にある「私は正しいことをしている」という(潜在的)意識は、時に不健全な対人関係を形成させてしまう危険性に対する援助者側の感性を麻痺させてしまう。この対人援助に伴う病理に対する病識を欠いたえげつないケアマネジャーだけにはならないよう努力して行きたいと思っています。
ケアプランふくしあ 木藤
2016年12月27日
補助線
人間は、自分自身の身の処し方を模索し、ある指針を見出そうとする時に、何らかの補助線を必要とする。本来、補助線の引き方というものは、それぞれの民族において宗教的文化伝承の中に引き継がれてきたはずだが、日本の場合、敗戦と近代化ということが重なって、補助線の引き方の指針となる文化伝承を社会は既に失っている。補助線を失った社会は地盤沈下を起こす。(福島原発は完全にアンダーコントロールされている。南スーダンは永田町よりはかなり危険だ。等々、政治の世界ではこの問題が見事に反映されている。)それでいて、このような問題を思考的に深化させていくようなトレーニングを受ける教育的機会が日本社会にある訳でもない。
敗戦前後までは国民の約50%が第1次産業に従事していた。山川草木国土悉皆成仏といったような感性が自然に涵養されていた。また、電化される前の家事労働は全て手作業であった。日常の生活を送ること自体の中に行的な要素が組み込まれており、そのことが人格を陶冶していた。現在では、第1次産業従事者は、5%未満である。そして日常の家事労働はボダン操作が中心である。人工を超えたものを畏怖する感性が研ぎ澄まされるような環境も無ければ、日常生活の中で、自ずから人格が陶冶されるなどということも、今の日本ではまず無い。山川草木国土悉皆成仏といったような感性を本当に身に沁みて持っている日本人は、もはや絶滅危惧種みたいなものである。明治生まれの祖母は濃厚な土の香りのする人だった。もはやそのような人と出会うことはないと思う。
陰徳を積むというという考え方の根底には、人生はこの世的なものだけで成り立っているのではないという、日本人の場合は思想性というより感性といったようなものが前提になって来たが、もはやそれも当てにならない。人生をこの世のみと観ずるか、あるいは、あの世と連綿とつながったものと観ずるかによって、生き方は大きく変わる。人間は、この世的ないし近代合理主義のみの価値観で生きれば生き方が下品になる。一方、彼岸的ないし神秘主義のみの価値観で生きれば、現実吟味能力を欠いた生き方になる。此岸に比重を置けばエゴが全面に出てくるし、彼岸に比重を置けばエゴが拡散してしまう。ではどうすればよいのか。自分で考えるしかない。現代は、各個人がそれぞれ自己責任において補助線の引き方から自分自身で見出していくしかない、という途方もない状況を生きて行かなければならないのかも知れない。補助線の引き方に絶対的な正解などというものは無いが、質の良し悪しはある。そう遠くはない将来、敬老される側に立つ身とすれば、その時、敬老されるに相応しい人間に果たしてなれているかどうか? また、年を取る。下品な人間にならぬよう一年一年、補助線の引き方をブラッシュアップしていかねば。
歴史の突端に立つ子供達
紺青の海の向ふから大きな朝日の正月が昇る。
新しい年を迎へた子供達が真赤に昇る。
あれは朝日で正月で子供達だ。
子供達は待たれてゐる、呼ばれてゐる、招かれてゐる。
真赤な正月だ。真赤な子供だ。真赤な自分だ。
真更に光つて、ふくらんで、燃えて、今こそ昇る。
どんな自分を見付けるか今年。
どんな自分を貰ふか今年。
河井寛次郎「六十年前の今」より
ケアプランふくしあ 木藤
敗戦前後までは国民の約50%が第1次産業に従事していた。山川草木国土悉皆成仏といったような感性が自然に涵養されていた。また、電化される前の家事労働は全て手作業であった。日常の生活を送ること自体の中に行的な要素が組み込まれており、そのことが人格を陶冶していた。現在では、第1次産業従事者は、5%未満である。そして日常の家事労働はボダン操作が中心である。人工を超えたものを畏怖する感性が研ぎ澄まされるような環境も無ければ、日常生活の中で、自ずから人格が陶冶されるなどということも、今の日本ではまず無い。山川草木国土悉皆成仏といったような感性を本当に身に沁みて持っている日本人は、もはや絶滅危惧種みたいなものである。明治生まれの祖母は濃厚な土の香りのする人だった。もはやそのような人と出会うことはないと思う。
陰徳を積むというという考え方の根底には、人生はこの世的なものだけで成り立っているのではないという、日本人の場合は思想性というより感性といったようなものが前提になって来たが、もはやそれも当てにならない。人生をこの世のみと観ずるか、あるいは、あの世と連綿とつながったものと観ずるかによって、生き方は大きく変わる。人間は、この世的ないし近代合理主義のみの価値観で生きれば生き方が下品になる。一方、彼岸的ないし神秘主義のみの価値観で生きれば、現実吟味能力を欠いた生き方になる。此岸に比重を置けばエゴが全面に出てくるし、彼岸に比重を置けばエゴが拡散してしまう。ではどうすればよいのか。自分で考えるしかない。現代は、各個人がそれぞれ自己責任において補助線の引き方から自分自身で見出していくしかない、という途方もない状況を生きて行かなければならないのかも知れない。補助線の引き方に絶対的な正解などというものは無いが、質の良し悪しはある。そう遠くはない将来、敬老される側に立つ身とすれば、その時、敬老されるに相応しい人間に果たしてなれているかどうか? また、年を取る。下品な人間にならぬよう一年一年、補助線の引き方をブラッシュアップしていかねば。
歴史の突端に立つ子供達
紺青の海の向ふから大きな朝日の正月が昇る。
新しい年を迎へた子供達が真赤に昇る。
あれは朝日で正月で子供達だ。
子供達は待たれてゐる、呼ばれてゐる、招かれてゐる。
真赤な正月だ。真赤な子供だ。真赤な自分だ。
真更に光つて、ふくらんで、燃えて、今こそ昇る。
どんな自分を見付けるか今年。
どんな自分を貰ふか今年。
河井寛次郎「六十年前の今」より
ケアプランふくしあ 木藤