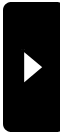› 介護の「ふくしあ」-スタッフブログ
2018年08月14日
神用語
『おじいちゃん、おばあちゃんの言うことが、時に分からなくなる。
「ホレ、アノ、ナニをアレしてくれる。あのナニを……」などと言いうのは、まだいいほうで、脈絡のない話の内容がつかめなくて、どうなっているのかと思わされる。こんなときに、老人性痴呆とか、老人ぼけという言葉が最近では一般に知れわたりすぎて、「うちのおじいちゃんも、老人ぼけになった」などとすぐに断定してしまう。ゆっくり落ち着いて聞いていると、わかる話でも、「ぼけている」と決めこんでしまっていると、わからなくなってしまう。老人のほうにしても、聞く者の態度にいらだってしまうので、言葉がスムーズに出なくなってしまい、ますます悪循環がひどくなってくるのである。
アイヌ(イヌイット)の人たちは、老人の言うことがだんだんとわかりにくくなると、老人が神の世界に近づいていくので、「神用語」を話すようになり、そのために、一般の人間にはわからなくなるのだと考える、とのことである。老人が何か言ったとき、「あっ、ぼけはじめたな」と受けとめるのと、「うちのおじいちゃんも、とうとう神用語を話すようになった」と思うのとでは、老人に接する態度が随分と変わってくることであろう。
「神用語」という言葉を考えだしたアイヌ(イヌイット)の人たちの知恵の深さに、われわれも学ぶべきである。』
河合隼雄 平成3年読売新聞夕刊コラムより
最近、新聞に、認知症にならない為のハウツー本に関する広告を目にしない日が無いくらいよく掲載されているような気が致します。また、『認知症高齢者は2012年で462万人(約7人に1人)2025年に700万人(約5人に1人)になると厚生労働省は推計しているようで政府の過去の推計を大幅に上回るペースで増加しているとのご見解で、こりゃあ大変だということで厚労省は認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)を策定しています。これらの対応の根底には「認知症」=「困りごと」といった図式がドミナントストーリーとして社会に共有されているという事を示唆している様に思います。人が誕生し、成長してやがて色気づく。歳を取ると白髪、皺、シミが増える。ガタも出る。やがて死が訪れる。この一連の流れは、人間の意志や意識とは関係ない。勝手にそうなるだけである。いわばDNA(神)用語の発現である。人間の意識的活動の最たるものは、言語と貨幣(経済)である。教育とはこの意識的世界への取り込み(洗脳)である。認知症とはその世界からの離脱(或いは脱却)である。人間的意識中心の価値観(人道)からすれば、認知症というのは、「困りごと」なのかもしれないが、私が思うに「認知症」も生命現象(天道)の中の一つの様相なのではないかということである。認知症という様相に対して、社会がどのように向き合っていくのかという事は、その社会にとっては文化力が試されているという事ではないだろうか。
ケアプランふくしあ 木藤
「ホレ、アノ、ナニをアレしてくれる。あのナニを……」などと言いうのは、まだいいほうで、脈絡のない話の内容がつかめなくて、どうなっているのかと思わされる。こんなときに、老人性痴呆とか、老人ぼけという言葉が最近では一般に知れわたりすぎて、「うちのおじいちゃんも、老人ぼけになった」などとすぐに断定してしまう。ゆっくり落ち着いて聞いていると、わかる話でも、「ぼけている」と決めこんでしまっていると、わからなくなってしまう。老人のほうにしても、聞く者の態度にいらだってしまうので、言葉がスムーズに出なくなってしまい、ますます悪循環がひどくなってくるのである。
アイヌ(イヌイット)の人たちは、老人の言うことがだんだんとわかりにくくなると、老人が神の世界に近づいていくので、「神用語」を話すようになり、そのために、一般の人間にはわからなくなるのだと考える、とのことである。老人が何か言ったとき、「あっ、ぼけはじめたな」と受けとめるのと、「うちのおじいちゃんも、とうとう神用語を話すようになった」と思うのとでは、老人に接する態度が随分と変わってくることであろう。
「神用語」という言葉を考えだしたアイヌ(イヌイット)の人たちの知恵の深さに、われわれも学ぶべきである。』
河合隼雄 平成3年読売新聞夕刊コラムより
最近、新聞に、認知症にならない為のハウツー本に関する広告を目にしない日が無いくらいよく掲載されているような気が致します。また、『認知症高齢者は2012年で462万人(約7人に1人)2025年に700万人(約5人に1人)になると厚生労働省は推計しているようで政府の過去の推計を大幅に上回るペースで増加しているとのご見解で、こりゃあ大変だということで厚労省は認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)を策定しています。これらの対応の根底には「認知症」=「困りごと」といった図式がドミナントストーリーとして社会に共有されているという事を示唆している様に思います。人が誕生し、成長してやがて色気づく。歳を取ると白髪、皺、シミが増える。ガタも出る。やがて死が訪れる。この一連の流れは、人間の意志や意識とは関係ない。勝手にそうなるだけである。いわばDNA(神)用語の発現である。人間の意識的活動の最たるものは、言語と貨幣(経済)である。教育とはこの意識的世界への取り込み(洗脳)である。認知症とはその世界からの離脱(或いは脱却)である。人間的意識中心の価値観(人道)からすれば、認知症というのは、「困りごと」なのかもしれないが、私が思うに「認知症」も生命現象(天道)の中の一つの様相なのではないかということである。認知症という様相に対して、社会がどのように向き合っていくのかという事は、その社会にとっては文化力が試されているという事ではないだろうか。
ケアプランふくしあ 木藤
2018年08月07日
タナトスからエロスへ
昭和62年に出版された「老人患者の心理と看護」という本を読んで、そこに記述されている老人像と今の老人像との違いに改めて時代変化の激しさを考えさせられました。約30年前の80歳代の中心は明治生まれです。この世代の人格形成に影響を与えたであろう基礎的教養は葉隠の「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」や教育勅語の国家道徳としての「忠」そして個人的道徳としての「孝」、いわゆる「忠孝」が中心だったのではなかと思います。若い時は共同体の一員として国の為に働き、親が老いればその世話をするのは当たり前で、逆に当人が年を取り介護が必要にになった時には、嫁が介護するのが当然であって、社会的サービスを使わざるを得なくなった場合には、申し訳ないあるいは情けないという心情が根底にあったように思います。
この書籍の中で著者の母親(66歳:T10年前後の生まれ、存命であれば98歳位)の事が次にように紹介されていました。「明治生まれの義母に仕え、戦時下及び戦後の困窮期に育児をしてきた母は、常に短剣を肌身離さずもち、『死に対して恐怖はなかった。いつでも死ねるという確信があった』と私の母(66歳)は今、話しています。」武家の血筋を引く方なのかも知れないが、昭和60年代にこの様な死生観を持ち続けている人が居たという事に驚きを感じました。
三世代世帯の割合は昭和60年頃は46%、平成26年は13%位です。自分の親は子供が面倒を見るのが当然という意識は昭和一桁世代で終焉を迎えたように思います。
江戸時代(特に人口が増加してきた中期)は、相当な間引きによる人口調整が行われていたらしい。昭和4~6年の大恐慌と大凶作の時代、東北農村では木の実やネズミなどで飢えをしのぎ、娘の身売りも全国で4万人を超えたと云う。もともと貧乏な国民なのである。歴史的な時間感覚で言えば昭和初期など昨日の出来事みたいなものである。江戸時代では、子供は5歳までは天からの預かりものという感覚があった。要は乳幼児死亡率が高かったので5歳前に亡くなる子供が多かったという事である。昭和であっても抗生剤がなかった戦前まで状況は同じようなものだったのだろう。想像するに戦前世代の多産な時代の親で自分の産んだ子供が一人も亡くならずに大人になったという親は少数派だったのではないだろうか。逆に戦後世代の親で自分の子供を亡くすという経験をしている親は圧倒的少数派であろう。昭和20年を境に親としての体験もそれだけ違うのである。
自然災害の多い風土と相まって貧乏が当たり前だった戦前に育った日本人にとって死は身近であり、『死に対して恐怖はなかった。いつでも死ねるという確信があった』というように、文化としてタナトス的な傾向を持っていたように思えます。それが敗戦を機に、戦後民主主義とエネルギーの大量使用による消費万能社会のもと生を謳歌するというエロス一辺倒へ激変した。
今の高齢者は言わばこの価値観の手のひら返しをされた世代である。T11年生まれの三浦綾子はそれまでは正しいと信じて教えていた教科書に、敗戦後は生徒に墨で塗りつぶすよう指導しなければならない事に強い慚愧を覚えキリスト教信者になった。S12年生まれの養老孟司氏は、教科書を墨で塗りつぶすよう指導された教育を、皮肉を込めこんな最高な教育はないだろと云う。昨日まで正しいと言われた事が今日からは正しくないという、要するに大人の都合など全くあてにならないという事を子供心に強く深く刻んだという事なのだろう。
この手のひら返しを経験され社会構造(共同体から個へ)の変化の中を懸命に生きて来た現在の高齢者の心の底流には、私たちの気持ちは今の人には分かってはもらえないというような諦めの気持ちと孤独感があるように感じられることがあります。
2025年からはいよいよ、戦後生まれのエロス一辺倒の申し子世代が80歳代を迎える事になります。若い時は学生運動や労働運動に、壮年期には高度経済成長とバブル経済と、比較的自由奔放に生きて来られた世代だが、親は大正生まれで親子間での価値観の捻じれを引きずってきた世代でもる。これから高齢期になって行く世代は、基本的には子供に世話になるよりも社会サービスを利用して行きたいという世代が年々増えて行くことになるのであろうが、その需要に応えられる社会的リソースがはたしてあるのかどうか?
S51年を境に病院死が在宅死を上回り、現在、自宅で亡くなるのは12%位である。大井玄氏が『人間の往生』の中で「医療技術による管理が進めば進むほど、死は家族から隠される傾向にある。死は、家族、そして社会一般から隔離され、抽象化され、結果としてほとんど神経症的に怖れられる現象となった」と指摘しているように、エロス一辺倒の価値観の中で「死」の抽象化が進んだが、「死」と「生」は言わば「地」と「図」のようなものである以上、「死」の抽象化が進むということは「生」の抽象化が進むということである。このようなパラドキシカルな時代に老人となって行く戦後生まれの第1世代高齢者はどのような老人像を後進に示されるのだろうか。
ケアプランふくしあ 木藤
この書籍の中で著者の母親(66歳:T10年前後の生まれ、存命であれば98歳位)の事が次にように紹介されていました。「明治生まれの義母に仕え、戦時下及び戦後の困窮期に育児をしてきた母は、常に短剣を肌身離さずもち、『死に対して恐怖はなかった。いつでも死ねるという確信があった』と私の母(66歳)は今、話しています。」武家の血筋を引く方なのかも知れないが、昭和60年代にこの様な死生観を持ち続けている人が居たという事に驚きを感じました。
三世代世帯の割合は昭和60年頃は46%、平成26年は13%位です。自分の親は子供が面倒を見るのが当然という意識は昭和一桁世代で終焉を迎えたように思います。
江戸時代(特に人口が増加してきた中期)は、相当な間引きによる人口調整が行われていたらしい。昭和4~6年の大恐慌と大凶作の時代、東北農村では木の実やネズミなどで飢えをしのぎ、娘の身売りも全国で4万人を超えたと云う。もともと貧乏な国民なのである。歴史的な時間感覚で言えば昭和初期など昨日の出来事みたいなものである。江戸時代では、子供は5歳までは天からの預かりものという感覚があった。要は乳幼児死亡率が高かったので5歳前に亡くなる子供が多かったという事である。昭和であっても抗生剤がなかった戦前まで状況は同じようなものだったのだろう。想像するに戦前世代の多産な時代の親で自分の産んだ子供が一人も亡くならずに大人になったという親は少数派だったのではないだろうか。逆に戦後世代の親で自分の子供を亡くすという経験をしている親は圧倒的少数派であろう。昭和20年を境に親としての体験もそれだけ違うのである。
自然災害の多い風土と相まって貧乏が当たり前だった戦前に育った日本人にとって死は身近であり、『死に対して恐怖はなかった。いつでも死ねるという確信があった』というように、文化としてタナトス的な傾向を持っていたように思えます。それが敗戦を機に、戦後民主主義とエネルギーの大量使用による消費万能社会のもと生を謳歌するというエロス一辺倒へ激変した。
今の高齢者は言わばこの価値観の手のひら返しをされた世代である。T11年生まれの三浦綾子はそれまでは正しいと信じて教えていた教科書に、敗戦後は生徒に墨で塗りつぶすよう指導しなければならない事に強い慚愧を覚えキリスト教信者になった。S12年生まれの養老孟司氏は、教科書を墨で塗りつぶすよう指導された教育を、皮肉を込めこんな最高な教育はないだろと云う。昨日まで正しいと言われた事が今日からは正しくないという、要するに大人の都合など全くあてにならないという事を子供心に強く深く刻んだという事なのだろう。
この手のひら返しを経験され社会構造(共同体から個へ)の変化の中を懸命に生きて来た現在の高齢者の心の底流には、私たちの気持ちは今の人には分かってはもらえないというような諦めの気持ちと孤独感があるように感じられることがあります。
2025年からはいよいよ、戦後生まれのエロス一辺倒の申し子世代が80歳代を迎える事になります。若い時は学生運動や労働運動に、壮年期には高度経済成長とバブル経済と、比較的自由奔放に生きて来られた世代だが、親は大正生まれで親子間での価値観の捻じれを引きずってきた世代でもる。これから高齢期になって行く世代は、基本的には子供に世話になるよりも社会サービスを利用して行きたいという世代が年々増えて行くことになるのであろうが、その需要に応えられる社会的リソースがはたしてあるのかどうか?
S51年を境に病院死が在宅死を上回り、現在、自宅で亡くなるのは12%位である。大井玄氏が『人間の往生』の中で「医療技術による管理が進めば進むほど、死は家族から隠される傾向にある。死は、家族、そして社会一般から隔離され、抽象化され、結果としてほとんど神経症的に怖れられる現象となった」と指摘しているように、エロス一辺倒の価値観の中で「死」の抽象化が進んだが、「死」と「生」は言わば「地」と「図」のようなものである以上、「死」の抽象化が進むということは「生」の抽象化が進むということである。このようなパラドキシカルな時代に老人となって行く戦後生まれの第1世代高齢者はどのような老人像を後進に示されるのだろうか。
ケアプランふくしあ 木藤
2018年07月31日
避難訓練をしました
消防署員の指導のもと消防訓練を実施しました。
まず火災報知機の鳴動で建物の外へ避難訓練をして、次に水消火器を使って消火訓練も行いました。

いざという時に、この訓練で学んだことを生かしたいと思います。
消火訓練では、初めて消火器に触ったという利用者様もいましたが、消防署員からの説明を受けてどうにか操作することが出来たようです。

夏の定番といえば浴衣ですが、ふくしあの家では毎年利用者様に浴衣を着ていただき季節を感じ取って頂けるようにしています。
浴衣の準備をして着付け方をお聞きすると丁寧に教えていただきました。「昔取った杵柄」とはこのことですね。


7月30日には吉川民友会の方々が来所して民謡を披露して下さいました。

司会者のおもしろいトークあり、三味線、尺八に合わせて民謡ありと大盛況でした。

8月も来所して下さいます。
私たちはこうした地域のボランティアの人たちにも支えられています。
本当にありがとうございます。
今月はふくしあの家が担当しました。
次回からはケアプランふくしあです。
まず火災報知機の鳴動で建物の外へ避難訓練をして、次に水消火器を使って消火訓練も行いました。
いざという時に、この訓練で学んだことを生かしたいと思います。
消火訓練では、初めて消火器に触ったという利用者様もいましたが、消防署員からの説明を受けてどうにか操作することが出来たようです。
夏の定番といえば浴衣ですが、ふくしあの家では毎年利用者様に浴衣を着ていただき季節を感じ取って頂けるようにしています。
浴衣の準備をして着付け方をお聞きすると丁寧に教えていただきました。「昔取った杵柄」とはこのことですね。
7月30日には吉川民友会の方々が来所して民謡を披露して下さいました。
司会者のおもしろいトークあり、三味線、尺八に合わせて民謡ありと大盛況でした。
8月も来所して下さいます。
私たちはこうした地域のボランティアの人たちにも支えられています。
本当にありがとうございます。
今月はふくしあの家が担当しました。
次回からはケアプランふくしあです。
2018年07月24日
オレンジカフェ開催
観測史上一番の41.1℃が熊谷で記録されたようです。
この暑さはいつまで続くのでしょうか。
夏祭りの定番と言えば金魚すくいですね。昔から日本人は金魚の泳ぐ姿を見て涼しさを感じていました。
上の写真は私たちが飼育している金魚です。なんだか見ているだけでも涼しくなりそうですが、もちろん利用者様には涼しさを感じて頂くだけでなく、水分も多めに摂っていただき熱中症予防をしています。
さて、7月19日は第一包括主催のオレンジカフェの日でした。
暑い中、たくさんの方に来所して頂きました。
この日は、大正琴の素敵な音色に合わせて、皆さんと懐かしい歌を合唱しました。
また利用者様に手品を披露していただいたりして、いつも通りの大盛況でした。

皆様、来月も是非おまちしています。
以上、今月はふくしあの家が担当しています。
2018年07月17日
暑い日が続きます☀
連日猛暑日が続きますが、皆様体調は大丈夫でしょうか。
吉川市でも水分をこまめに摂取して熱中症に気を付けてくださいと放送が流れていますね。
ふくしあでもスポーツドリンクやジュースなど様々な飲料水を用意し、熱中症に気を付けています。
さて、そんな暑い中、すくすくと育ってくれているのが、ふくしあの庭のキュウリ、トマトさん達です。
利用者様と一緒に収穫し、包丁で薄く切って頂き、浅漬けにして皆様と頂きました。
取れたての自家製キュウリはやっぱり 「おいしいね~」と大変好評でした。


16日は松伏の公民館で行われている絵画展にお邪魔させて頂きました。
とても素敵な作品がたくさん飾られていて、皆様熱心に鑑賞されていました。


さて、今週7月19日(木)はオレンジカフェが開催されます。
皆様のお越しをお待ちしています。
以上、ふくしあの家が担当しました。
吉川市でも水分をこまめに摂取して熱中症に気を付けてくださいと放送が流れていますね。
ふくしあでもスポーツドリンクやジュースなど様々な飲料水を用意し、熱中症に気を付けています。
さて、そんな暑い中、すくすくと育ってくれているのが、ふくしあの庭のキュウリ、トマトさん達です。
利用者様と一緒に収穫し、包丁で薄く切って頂き、浅漬けにして皆様と頂きました。
取れたての自家製キュウリはやっぱり 「おいしいね~」と大変好評でした。
16日は松伏の公民館で行われている絵画展にお邪魔させて頂きました。
とても素敵な作品がたくさん飾られていて、皆様熱心に鑑賞されていました。
さて、今週7月19日(木)はオレンジカフェが開催されます。
皆様のお越しをお待ちしています。
以上、ふくしあの家が担当しました。
2018年07月10日
梅雨明けしました
皆様お久しぶりです。
今月はふくしあの家が担当させて頂きます。
今年は異例の早さで梅雨明けが発表されました。
ふくしあの家では、水分をこまめに摂って頂いて、熱中症対策をしています。
7月に入り暑い日が続く中、室内では11月の市民祭りの作品作りなどをされ皆様精力的に活動されています。
ここふくしあの庭ではヒマワリの花が咲き始めました。
いよいよ夏本番ですね。

7月といえば七夕です。
今年も皆様に手伝って頂きながら、七夕の飾り付けをしました。
利用者様は短冊にどんな願いをこめたのでしょうか。

そして7月7日の七夕当日の昼食は七夕特別メニューでした。
利用者様は大満足のご様子でした。

以上
ふくしあの家でした。
今月はふくしあの家が担当させて頂きます。
今年は異例の早さで梅雨明けが発表されました。
ふくしあの家では、水分をこまめに摂って頂いて、熱中症対策をしています。
7月に入り暑い日が続く中、室内では11月の市民祭りの作品作りなどをされ皆様精力的に活動されています。
ここふくしあの庭ではヒマワリの花が咲き始めました。
いよいよ夏本番ですね。
7月といえば七夕です。
今年も皆様に手伝って頂きながら、七夕の飾り付けをしました。
利用者様は短冊にどんな願いをこめたのでしょうか。
そして7月7日の七夕当日の昼食は七夕特別メニューでした。
利用者様は大満足のご様子でした。
以上
ふくしあの家でした。
2018年07月01日
梅ジュースの感想は・・・
6月にはじめにみんなで作った梅シロップも氷砂糖が溶け、
梅がしわしわになりエキスがしみ出て完成しました。

コップに梅シロップを入れ、お好みの量の水で割ったら完成です。
水の代わりに炭酸水でもいいです。
早速、みんなで飲んでみると『おいしくできたね』、『いくらでも飲めちゃうわ』と大変好評です。


これからの季節、お風呂上りや体操後の水分補給に活躍してくれそうです。
残った梅はそうめんに入れて一緒に食べてもおいしいです。
何より酸味と甘みのバランスがいいようで普段、あまり飲まない方もよく飲んで下さいます。
飲んで一言・・・

『うめ~』
ふくしあ吉川 高橋でした。
梅がしわしわになりエキスがしみ出て完成しました。
コップに梅シロップを入れ、お好みの量の水で割ったら完成です。
水の代わりに炭酸水でもいいです。
早速、みんなで飲んでみると『おいしくできたね』、『いくらでも飲めちゃうわ』と大変好評です。
これからの季節、お風呂上りや体操後の水分補給に活躍してくれそうです。
残った梅はそうめんに入れて一緒に食べてもおいしいです。
何より酸味と甘みのバランスがいいようで普段、あまり飲まない方もよく飲んで下さいます。
飲んで一言・・・
『うめ~』
ふくしあ吉川 高橋でした。
2018年06月30日
ハーモニカの音色
梅ジュースも梅を凍らせてから作ったおかげで、だいぶ砂糖も溶けて、梅のエキスが出てきています。
梅が瓶の中でシワシワになってきています。
もうすぐ飲めそうかな?
さてふくしあではオレンジカフェを毎月開催しています。
3週目に行われ、偶数月は金曜日。奇数月は木曜日に開催されています。
どなたでもふらーっと来て参加してください。
ふくしあの雰囲気もわかるのではないdしょうか。
今月はボランティアの方が来て下さりハーモニカを演奏して頂きました。
その演奏に合わせて歌をたくさん歌いました。
青い山脈やリンゴの歌など歌にまつわる話も入れながらなので、参加された利用者様もへ~とうなずかれていました。
普段から歌うことの多い曲を選んでくださったので、よく声も出ていたのではないでしょうか。
ありがとうございました。
梅が瓶の中でシワシワになってきています。
もうすぐ飲めそうかな?
さてふくしあではオレンジカフェを毎月開催しています。
3週目に行われ、偶数月は金曜日。奇数月は木曜日に開催されています。
どなたでもふらーっと来て参加してください。
ふくしあの雰囲気もわかるのではないdしょうか。
今月はボランティアの方が来て下さりハーモニカを演奏して頂きました。
その演奏に合わせて歌をたくさん歌いました。
青い山脈やリンゴの歌など歌にまつわる話も入れながらなので、参加された利用者様もへ~とうなずかれていました。
普段から歌うことの多い曲を選んでくださったので、よく声も出ていたのではないでしょうか。
ありがとうございました。
2018年06月15日
梅ジュースのレシピ
お待たせいたしました。
それでは梅ジュース作りのレシピです。
材料は2つだけです。
梅と同量の氷砂糖です。あとそれらを入れる容器があればできちゃいます。
①梅のへたをとります。
竹串や楊枝だと先がつぶれてしまい上手く出来なかったので、フォークで行いました。

②梅をよく洗い、乾かします。
③梅をフォークで刺してエキスがしみやすいようにします。




④それを一晩、凍らせます。凍らせることで、細胞壁が壊れてエキスが出やすくなはやくり、はやく出来ます。
⑤容器の中に梅と氷砂糖を交互に入れて準備は終わりです。

だんだんと砂糖が溶けていきますので、容器を振って下さい。

だいたい1ヶ月で梅ジュースのシロップが完成になります。![]()
各工程を利用者様に手伝って頂いたので、7kgの梅の準備もあっという間にできました。
今年はいつも以上にたくさん飲めそうです。
今月の終わりには完成した梅ジュースについて報告させていただきます。
それでは梅ジュース作りのレシピです。
材料は2つだけです。
梅と同量の氷砂糖です。あとそれらを入れる容器があればできちゃいます。
①梅のへたをとります。
竹串や楊枝だと先がつぶれてしまい上手く出来なかったので、フォークで行いました。

②梅をよく洗い、乾かします。
③梅をフォークで刺してエキスがしみやすいようにします。




④それを一晩、凍らせます。凍らせることで、細胞壁が壊れてエキスが出やすくなはやくり、はやく出来ます。
⑤容器の中に梅と氷砂糖を交互に入れて準備は終わりです。

だんだんと砂糖が溶けていきますので、容器を振って下さい。

だいたい1ヶ月で梅ジュースのシロップが完成になります。
各工程を利用者様に手伝って頂いたので、7kgの梅の準備もあっという間にできました。
今年はいつも以上にたくさん飲めそうです。
今月の終わりには完成した梅ジュースについて報告させていただきます。
2018年06月06日
6月の始まり
6月になりましたね。いかがお過ごしでしょうか。
ふくしあ吉川では、毎年恒例の梅ジュース作りを始めました。
今年は利用者様のお宅から声をかけて頂き、梅を取らせて頂きました。
普段送迎で何度も行っているのに気づきませんでしたが、大きな木にたくさん実をつけていて驚きました。


男性利用者様と、お邪魔させて頂き、たくさんの梅を取ることができました。
ありがとうございました。
たくさんの梅を頂くことができ、美味しい梅ジュースがたくさん飲めるかと思うと今から楽しみです。
今年は梅ジュースだけでなく、梅のシャーベットなども作ろうとスタッフと考えています。
次回は梅ジュース作りをお送りいたします。
お楽しみに
ふくしあ吉川 高橋でした。
ふくしあ吉川では、毎年恒例の梅ジュース作りを始めました。
今年は利用者様のお宅から声をかけて頂き、梅を取らせて頂きました。
普段送迎で何度も行っているのに気づきませんでしたが、大きな木にたくさん実をつけていて驚きました。
男性利用者様と、お邪魔させて頂き、たくさんの梅を取ることができました。
ありがとうございました。
たくさんの梅を頂くことができ、美味しい梅ジュースがたくさん飲めるかと思うと今から楽しみです。
今年は梅ジュースだけでなく、梅のシャーベットなども作ろうとスタッフと考えています。
次回は梅ジュース作りをお送りいたします。
お楽しみに
ふくしあ吉川 高橋でした。